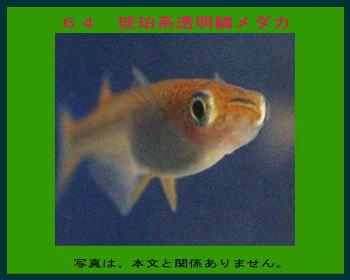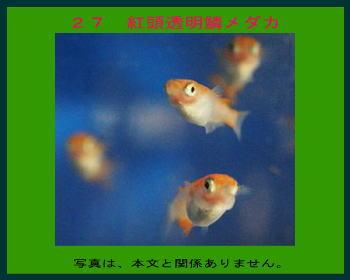|
第1話 目覚めの朝
|
|
それは、何時頃のことだったろう。
気がつくと、薄ぼんやりとした明かりが見える中を黒い影が動いていた。
明かりは白くなったかと思うと灰色が掛かり、暗くなったかと思うと急に白く輝くように変化していた。
黒い影は、時に速く、時に遅く、手前を大きな影が通り過ぎれば、遠くでは小さな影の塊がどちらへとも無く行き来している様であった。
無意識のうちにどれくらいの時間眺めていたのだろう、その景色は次第に暗い時間が長くなり、色は薄墨から紫の世界へ、そして、青さが次第に増していく。動き回っていた黒い影は少しずつ数が減り、青の世界が暗灰色へと変わっていくのに従って見られなくなった。
その後、暗闇の世界が襲ってきたのだろう、ボクは眠ってしまったようだ。
「ワーッ。」
大きな眼がボクを見ているのに気付いて目が覚めた。
大きな眼は、眼の先にある大きな口でボクの周りを穿り返していた。
「止めてくれぇー。」
聞こえるはずも無い声を上げた。
一向に止める様子も無く、ボクの体をゆすってくる。
「ワアッ。」
体が浮きそうになった時、もう一つの眼が現れ、もつれ合いながら大きな体をボクにぶつけるように掠めて行き去った。
「助かったー。」
周囲は、同じような景色が広がっていたが、この前とは違ってはっきりと良く見える。
遠くに明るい光の差す場所があり、明るい部分は強く輝いたり陰ったりを繰り返している。中では、ヒレを動かして泳ぐ生き物がどちらとも無く動き回っている。その生き物は、陰では黒い塊に見えるが、明るいところでは白く輝いて見えるのだった。
よく見ると、ボクは透明な丸いものに閉じ込められているみたいだ。
ボクの体は、この丸いもののおかげでフワリフワリとさまよい捕まえにくかったのだろう。そのおかげで、大きな眼の持ち主から逃れることが出来たみたいだ。
「ムムッ、ボクはどうすればよいのだろう。このまま、この丸いものの中に居てよいのだろうか。」

|
|
第2話 誰かが見ている
|
|
ふと、斜め後ろを見ると小さな丸い透明なカプセルの中に眼がある物体に気付いた。
でも、よく見えない。
向きを変えようと腰を振ったり頭を振ったり、もがいてもがいてやっとのことで少し向きが変わった。
「よし、もう一度。」
腰を振って頭を振って。もう一度。
腰を振って頭を振って。
繰り返すうちにスムーズに向きが変えられるようになった。
「ようし、もう一度。」クルリ。
「もう一度。」クルリ。
「ワアイ。」
向きを変えることが面白くなったボクは、夢中で「クルリ」を繰り返していた。
自由に向きが変えられると色々と違った周りの景色が見えてくる。上の方は青白く輝く世界だけれど、下は黒い岩がごろごろしている。後ろを向くと、緑の林になっていて、ボクがいる丸い透明なものは林の一部につながっているみたいだ。前を見ると、広い空間の中に、時々、小さな生き物が流されるように動いていったり、大きな眼の持ち主がすばやく通り過ぎていく。
「そうだった。さっき確認しようとしていた丸いものは。」
と思い斜め後ろに向き直すと、斜め後ろにあった丸い透明なカプセルの中でも、不思議そうにこちらを見ている眼があった。
「こんにちは。」
あいさつしたけれど、聞こえてないだろうなあ。
今までボクがクルクル回っていたのを見られていたのだろうと思うと照れくさくなって、背を向けた。
やがて周囲は次第に暗くなり、あの時と同じように暗闇に包まれた。
次に気付いたのは、上の方は赤く染まり、反対側からの光が差し込もうとしている時だった。
「斜め後ろの子はどうしているだろう。背中を向けたままで悪いことをしたなあ。気にしていることだろう。」
そう思い、「クルリ。」と斜め後ろへ振り返った。
けれど、その子の姿はそこには無かった。

|
|
第3話 誕生
|
|
「何処へ行ったのだろう。」
目を凝らしてくまなく捜した。
「たしかに、この辺りにいてじっとボクを見ていたのに。丸いカプセルの中に入っているのだから遠くへは行けないだろうし。」
次第に明るくなり、光の向きが上から降り注ぐようになった頃、少し離れたところに丸い透明なものが浮かんでいるのが見えた。
「あれだ。でも、空っぽみたいだ。」
「まさか!」
大きな眼のやつに襲われてしまったのだろうか・・・。
ボクは、しばらく呆然として中身のなくなった透明な丸いものを見ていた。
それが、次第に光の束に溶け込んで見えなくなる頃、この前のように黒い影がにぎやかに泳ぎまわるようになった。その時、下の方から小さな目をした可愛い子が上がってきて、何か言いたそうにボクの方を見ている。
「そうか、君は斜め後ろにいた子だね。」
「丸いものから抜け出して泳げるようになったんだ。」
「良かった。」
ボクは、うれしくてグルグルと回転した。
そのはずみで尻尾の部分が透明な殻を破り飛び出してしまった。
尻尾が殻に挟まって、もがいても抜けないし「クルリ」と回ることもできない。
「動けないよー。ハアー。疲れた・・・。」
結局、尻尾を殻の破れ目から突き出したままで夜を迎えることになった。
その子は、しばらくボクのみっともない様子を見ていたようだが、ボクがまだ動けないと分かったのか何処かへスィーと行ってしまった。
「出してくれよー。」
次の日になると、尻尾の辺りの殻が少し柔らかくなっているのに気付いた。
「よし、もう一度やってみよう。」
ボクは力いっぱい尻尾を振って、後ずさりするように動いた。目の前が殻から少し離れた。
「少し、後ろへ下がったみたいだ。」
「もう一度。」
尻尾を振るたびに少しずつ後ろへ動いていくのが分かる。
体をくねらせると大きなお腹も少しずつ殻を破っていく。
「あと少し・・・。」
お腹が殻から滑り出た。すると、スルリと丸い透明なカプセルから抜け出すことができた。
「やった!」
と喜んだものの、どうすれば泳げるのか分からない。
ボクは、そのままゴロゴロとした岩の間にゆっくりと沈んでしまった。

|
|
第4話 初めての仲間 |
|
ボクは、しばらく動く気になれなかった。
初めて知った水の世界で、緩やかに揺れ動く流れに身を任せて、まるでゆりかごにでも乗っているかのように漂っていた。
遠くの方で、プクプクと音がしている。
その辺りは、相変わらずザワザワといった感じで影が動き回っている。
ずっと、こうしていたい気分だったけれど、そうは行かないようだ。
昨日、ボクが回っているのを見ていた子が、フワリフワリと流れるように舞い降りてきた。
「何をしているの。」
「別に・・・。無の境地かな?」
「変なの。」
「君は、ボクの斜め後ろのカプセルにいた女の子だよね。」とボクが言うと、
「何言っているの、あなたのカプセルが私の後ろにあったのよ。あなたは後ろを向いていたけれど。」と返してくる。
「いや、そんなことは無い。」
と言い返そうとしたけれど、反論しても無意味に思えたから、それ以上何も言わなかった。
「夜は、何処に居るんだい。」と聞くと、
「そこの林の向こうに、たくさん仲間が集まっているの。私も夜はそこにいるわ。」と教えてくれた。
今は動く気になれなかったボクは、
「じゃあ、明日行ってみるよ。」
「じゃあ、また。」 と言って別れた。
その子は、スイスイというよりもフワフワという感じのぎこちない泳ぎ方で林の方へ消えていった。
その日は、他に何事も無く静かに夜が過ぎていった。
次の日、ボクは林の向こうへ探検に出ることにした。
重い腹をあげて尻尾を振ったが、あれよあれよと言う間に林とは反対の方向へ流されてしまう。
懸命に、胸ビレを動かして尻尾を振り続けても一向に前へ進まない。
その場所に留まるだけで精一杯だった。
何度もやってみたが同じこと。
「ふうーっ、ちょっと休憩。」
「これじゃあ、何処へも行けないなあ。」
しばし考えてみた。
「そうだ、流れに逆らってまっすぐに林の方へ行こうとするから無理があるんだ。流れに乗って林に沿うように回り込めばいいんだ。」
ボクは、流れに対して斜め方向へ進むことにした。
流されては進み、また流されては進みの状態で、随分遠回りではあったけれど、少しずつ林の方へ進んでいた。
「あと少し。」
やっとの思いで林の横まで来たとき、そこで逆流していた水の勢いに乗ったボクは林の奥へ押し流され、林を通り抜けて、皆が集まっている所へ飛び出した。
「やあ・・・。コンニチハ。」
そばにいた一匹が、
「唐突なやつだなあ。」
昨日の彼女が、
「この子よ、そう、昨日私が言っていた子。待っていたのよ。こっちへいらっしゃい。」
ちょっと恥ずかしかったけれど、仲間に入れてもらえそうだ。
ここには、スラリとしたカッコいいやつも居れば、デブッチョが居たり、オチビさんが居たり、それぞれ個性のある子が集まっていた。こうしてよく見ると、彼女もスマートでキュートだね。(なんちゃって。)
デブッチョとオチビとは、すぐ仲間になれた。
早速、泳ぎ方も教わった。
「ヒレをこう動かして、尻尾はこんな風に。」と、デブッチョがやって見せてくれるので、真似してみる。
「そうそう、大分うまくなったね。」
「どんなもんだい。」と自慢げに言ったら、
「別に、威張るほどのことでも無いだろう。泳ぎも覚えたし、何して遊ぼうか。」とデブッチョに交わされた。
オチビは、すぐに「カクレンボ。」なんてはしゃいでいた。
こうして、すぐに打ち解けた仲間たちは、数日の間に色々と遊びを覚えたし、徐々に速く泳ぐことが出来るようになってきた。
狭い住処だけど、楽しい日々だった。
でも、周囲を見渡してみると、少し大きい子たちは何だか皆元気が無いと感じていた。
「どうしたんだい。」
ボクは恐々聞いてみた。
すると、一匹の子が、「腹減ったよう。もう、一週間も何も食べていないんだ。」と言った。
今まで全く気にしていなかったけれど、そういえば、何かを食べなければならないと言うことをボクは知らなかった。

|
|
第5話 長い一日
|
|
「何かを食べないといけないの?」
「当たり前じゃないか。このまま何日も何も食べなければ死んでしまうよ。」
別の一匹が、
「上の方には食べ物が一杯あるっていうのに、あのデッカイやつらが居座っているから食べに行けないんだ。」と明るい光が差すほうを見上げた。
そういえば、大きな眼をしたやつが、水面にある何かを夢中で追いかけている影を何日も眺めていたっけ。
「隅っこの方で、邪魔しないように食べれば良いんじゃないの。」
と、ボクが言うと、その子は、
「何言ってんだよ、やつらにすればボク達も食べ物なんだから、近づいたら終わりだよ。この一週間ほどの間にも、たくさんの同僚が食われているんだから。」と物騒な話をした。
ボクは、しばらく言葉が出なかった。
ボクには、どうすればいいのかなんて分かるすべも無かった。
上の方では、相変わらずたくさんの黒い影が行き来していた。
それを見ていた一匹の子が、
「もう駄目だ! 何か食べないと死ぬ・・・。」
と言って、狂ったように上がっていった。
「今は駄目だよ。危ない。」
止めようとしたが、間に合わなかった。
丁度、その時、すぐ上を大きな影がよぎり、その子は一瞬のうちに影に吸い込まれてしまった。
ボクは、振るえが止まらなかった。
仲間たちも皆、底に引っ付くようにして怯えていた。
一匹の子が、振るえながら口を開けた。
「ボクも食われそうになったことがあるんだ。」
その子が言うには、食べ物が水面に降ってきた後、しばらくして頭の真上に小さな食べ物が少し流れて来ているのが見えたので、真っ直ぐに浮き上がろうとしたら、動いている物を見つけたからだろうか、大きなやつが追いかけてきて飲み込まれそうになった。水の勢いで流される様に逃げることができたので、大きなやつは浮いていた食べ物を口にして行ってしまった。おかげで、飲み込まれずに済んだ。とのことだった。
「でも、何か食べないと駄目なんだろう?」と聞くと、
「少しなら流れてくることもあるけど、ぜんぜん足りないからね。」と、その子の言葉に、
「余程運が良くないと、ここでは食べ物に在りつけないよ。」と、また別の子が、
「あんなのに、パクッと遣られる位なら、ここで流れてくる食べ物を待っていた方がましだよ。」
「でも、流れてこなければ死んでしまう。」
皆、口々に、話しかけてきた。
「・・・・・。」
ボクは、返す言葉も何も出てこなかった。
「もう、我慢できないよ。」
また、一匹の子が浮き上がろうとした。皆、必死で止めようとしたが、
「行くしかない。」と言い残し、影が泳ぎ回る方へ向かって行った。
その子が泳いで行く後を、大きな影が追って行くのが見えた。
その後も、大きな影は何度と無くボク達の上を通り過ぎていく。
「何故なんだ。ボク達が何をしたと言うんだ。」
皆、見つからないように石の間に隠れて過ごした。
そのうちに周囲は暗くなり、恐怖の中で夜が過ぎていった。

|
|
第6話 生きるために |
|
次の朝、ボクは体に重いものが乗っかってきて目が覚めた。
乗っかってきたのは、昨日、食われそうになったことがあると話していた子だった。
ボクよりずっと大きい子なのに、力なく底を這うようにして進もうとしている。
「どうしたんだ。」
とボクが聞くと、
「もう駄目だ。体がしびれて動けなくなってきた。」
「しっかりしろよ。何か食べ物を探してくるから待っているんだ。」
ボクは、必ず探して持ち帰ると決心して、やつらが静かにしている間に水面近くの食べ物を探しに行くことにした。
林の間を浮き上がれば見つからないだろう。
ボクは、林の中の葉から葉へと隠れながら、少しずつ上がっていった。上に行くほど水の流れは強く、葉がボクの体に当たってくる。その度に、林の外へ飛ばされそうになりながらも、どうにか水面へ出ることができた。
葉の間から見渡すと、先の方にある葉が水面から少し出ていて、葉に沿って白っぽいものがポツポツと浮いている。
「たぶん、あれは食べ物だろう。」
ボクは、流されそうになりながらも葉に沿って浮き上がり、白い塊が浮いている所へたどり着いた。
「クンクン。」
少しだけれど、良い匂いがする。
「パクッ。」
一口食べてみた。生まれて初めての食べ物だった。
「おいしい。」
思わず叫びそうになった。
有頂天になって、「もう一つ。」と、その先にある食べ物を口に入れようと近付いた時、ゴオーと唸るような水音がしたと思うと、強い波しぶきとともに大きな眼と口が襲ってきた。
「ワアー。」
タッチの差で葉の下へ隠れて交わす事が出来たと思いきや、その大きな眼のやつは反転して、またこちらへ向かって来る。
「もう駄目だ・・・。」
と思った時、遠くの水面でザワザワと音がして周りがざわめき立つと共に、たくさんの食べ物が降ってきた。
それに気付いた大きな眼のやつは、食べ物が流れて来る方へ行ってしまった。
「助かったあー。」
ボクは、そこから一歩も動けなくなり、大きな影が盛んに食べ物を啄ばんでいる様子を見ているだけだった。
でも、見ていて一つ気付いたことがあった。
やつらは、大きい食べ物ばかりを選んで食べている。小さいものは食べられずに流れてきて、林の周りにも一杯漂っているではないか。
しかも、やつらは食べることに熱中していて、他のものは全く見えていないようだ。
ボクは勇気を出して、もう一度水面へ出てみた。
辺りは一面に良い匂いが漂って、数え切れないほどの食べ物が浮いていた。
「パクパク。」
ボクは、お腹一杯食べ、口に銜えきれる限り銜えて林沿いに帰途に着いた。
仲間の住処では、たくさんの子が待っていた。
「一人で出かけていったと聞いて心配していたんだよ。」と一匹が言うと、
「上の方で大きな水音がしたので、襲われたんじゃないかと思って。」
「無事帰れて良かった。」
皆、口々に話しかけてきた。
ボクは口に銜えた食べ物を置いて、
「大丈夫だったよ。」と笑った。
皆の顔を見て、ちょっと英雄気取りだったけれど、彼女だけは違っていた。
「バカ、無茶なことをして。」
悲しい眼をしてボクを見ていた。
ボクは、自分のことを心配してくれる子が居るということが、とてもうれしかった。
「心配かけてごめんよ。もう自分だけで行ったりしないから。そうだ、あいつに食べ物をあげなければ。」と、横たわったままの子の所へ急いで近づいた。
「ほら、食べ物を持ってきたよ。」と、差し出すと、
「ありがとう。」
でも、その子はほとんど動くことも出来ず、息も絶え絶えだった。
「少しでも食べれば元気が出るよ。」
ボクは、食べ物を口に銜えて、その子の口元へ持っていったが食べようとしなかった。
「ありがとう。ボクのためにそこまでしてくれて、本当にうれしかったよ。ボクにはもう食べる力が無いから、元気な仲間たちが生きて行けるように食べ物を分け合ってくれよ。皆が腹いっぱい食べられるように、食べ物の探し方を教えてやっておくれよ。約束だよ。」
そして、「もっと早く君に会えたら良かった。」
ボクは泣きながら食べ物を口に押し込もうとしたが、もう、その口は動かすことも出来なくなっていた。
次の日の朝、その子の動かなくなった体は静かに浮き上がり、まるで旅立ちのように流れに乗って林の向こうへと消えていった。
「さようなら。きっと、約束は守って見せるからね。」
今日は、皆を連れて食べに行こうと決めていた。
「皆、まとまって食べに行こう。集まって近づけばきっと大丈夫だから。」
と、ボクの言葉に一匹の子が、
「そうだね。このまま底で怯えていても仕方ないし。」と言うと、
「お腹も空いてきたし。」
「作戦はあるのかい。」と、皆、乗り気になってきた。
ボクは、
「OK! 林沿いに浮き上がっていって、食べ物が舞い降りてくるのを葉の影で待つんだ。ザワザワと音がして食べ物が落ちてくると、やつらは食べるのに夢中になるから、その時が狙い目だよ。葉に引っ付いて水面まで上がれば、良い匂いがしてたくさんの食べ物が流れてくるから、一斉に食べ物に飛びついてサッサと引き上げてくれば良い。」と説明した。
皆、喜び顔して、
「ようし、口一杯銜えて持って帰るよ。」
「うーん、楽しみだね。」
「皆で集まっていれば、怖くないよね。」
「そうだ、出掛けよう。」
ボクの周りには、十数匹の仲間が集まっていた。
「さあ、出発だ!」
僕たちは一団となって、林の中を枝伝いに駆け上がった。
皆、水面近くの葉の下に思い思いに隠れた。
水面の先の方には、日差しにキラキラと輝いた赤い魚が、盛んに動き回っている。
「アッ、やつらは皆、赤い色をしているんだ。」
今まで、薄暗い底に隠れて見ていたので影しか知らなかったし、昨日は恐怖で色を気にする余裕も無かったから、気が付かなかったのだ。
「こうして見ると綺麗だね。」
と、ボクが囁くと、
「余裕だね。ボクなんて恐ろしくて目に入らないよ。」
と、近くにいた子がヒソヒソと答えて来た。
どれほどの時間が過ぎたのだろう。食べ物は中々降って来なかった。
「お腹空いたよー。」
叫んだ声に気付いたのか、大きな眼のやつが一匹こちらへ近づいてきた。
「隠れろー。」
僕たちは葉の裏に引っ付くようにして押し黙った。
やつは、林の周囲をぐるっと一周して、向こうへ行ってしまった。
気付かれなかったようだ。
「良かったー。」
それから、ただひたすら待ち続けた。
「疲れたね。」
「今日は降ってこないんじゃないか。」
諦めかけた時、遠くの方でザワザワと音がした。
やつらも待ち疲れて騒いでいるようだ。
一瞬、辺りが少し暗くなった後、また、ザワザワと音がしてたくさんの食べ物が降ってくるのが見えた。
「やった!」
と叫びながら、ボクは葉の先へ出て、やつらが集まっている方を見た。
水面に頭を向けてパクパクと音がするかのように動いている口が見える。
程なくして、少し近い所へもザザッと食べ物が降ってきて、辺り一面に良い匂いが漂い始めた。
「昨日と同じだ。」
皆は、
「これなんだね。」
「すごいや。」
ボクが、
「やつらは大きい食べ物に夢中になっているから今なら大丈夫だ。」
と言う合図に、一斉に水面に出て食べ始めた。
「ウマーイ。」
「やったね。」
皆、うれしそうに口一杯ほおばっていた。
「食った。食った。」
満足した僕たちは、早々に林沿いに引き上げることにした。
それから、僕たちは毎日、食べ物が降ってくる頃を見計らって水面近くに上がって食べるようになった。

|
|
第7話 違う世界 |
|
おかげで、仲間たちも、どんどん大きくなって来ていることが分かった。
彼女は、いつものように小さい子達を連れて食べに来ていた。
「やあ、また新しい子達かい。」と、ボクが聞くと、
「そうよ、数日前に生まれた子たちで、底の方にじっとしていたから連れて来たのよ。」
「君みたいな子が世話してくれて、ラッキーな子達だね。」
と言いながら、ボクは、あの忌まわしいやつらの方を見た。
その時、ボクの目に入ったのは、赤い大きなやつらの間で食べ物を突いている小さい子だった。
「あれえ、あの子、ボクよりずっと小さいんじゃないか。よく平気であんな大きいやつらと一緒に居られるなあ。」
ふと、その少し先を見ると、もう一匹、ウロウロしている小さい子が居ることに気付いた。
ボクは、そのことが気になって仕方が無かった。
次の日も見ていると、昨日と同じように大きな赤いやつらに混じって食べている。
「何故、平気で居られるのだろう。ボク、聞いてくるよ。」と言うと、
「止めなさいよ。襲われるわよ。」
止めようとする彼女の忠告も聞かずに、ボクは大きなやつらが泳ぎ回る所へ近づいて行った。
確かに恐ろしい。
でも、もしかしたらやつらは敵ではないのかもしれない。
ボクの好奇心は恐怖より強かった。
大きいやつらに気付かれないように、小さなその子が端の方へ寄って来た時に、スーッと近づこうとしたが、その前に、ボクに気付いたのだろう大きな眼で覗き込んで来る者がいた。
「ブワッ。」
ボクが驚いて逃げようとした時、大きなやつは信じられない声を掛けてきた。
「坊や、こんにちは。」
ボクは、振るえながら小声で答えた。
「コンニチハ。」
「あなた、余り見かけない子ね。」
ボクが怯えているのを悟ったのか、
「怖がらなくてもいいのよ。ここは、皆の家なのだから。一緒にお食事していきなさい。」
と、誘いかけてくれた。
ボクは、恐々、震えながら大きな赤い魚たちの群れの中で食事をした。
魚たちは、口々に声を掛けてくる。
「おや、初顔かい。」
「いつも端っこの底の方にいるチビたちの仲間だね。」
「おお、お前も美味そうだな。食ってやろうか。」
「よしなよ。怯えてるじゃないか。今はそんな必要無いだろう。」
「ハハハ、冗談だって。」
おっかなびっくりのボクの様子が、余程可笑しかったのだろう。
「これじゃ、ほとんど食べた気がしない。」
ボクは不機嫌な態度で、「帰る。」と言った。
すると、先ほどのおばさんが、
「怒らないでね。皆、悪気は無いのだから。今度は、あなたのお友達も連れて来ると良いわ。」と、ボクの住処の近くまで送ってくれた。
ボクは、あのいつも凶暴に襲ってくるやつらが、あんなに仲良く食事していることに半信半疑であった。
住処へ帰ったボクは、今日あったことを仲間たちに話して聞かせた。
皆の反応は様々だった。
「なんか、怪しいなあ。僕たちを太らせて食べようとしているのじゃないか。」
「ボクは行ってみたいね。面白い探検ができそうだ。」
「やつらと仲間になれば安心かもね。」
「でも、小さい子は危険よ。」
ボクは、しばらく皆が言うことを静かに聞いていた。
「よし、明日もう一度行こう。行きたい者は明日の朝、集まってくれ。」
「分かった。」と、
何匹かの仲間は一緒に行くことを約束して、記念すべき一日は幕を閉じた。
次の日の朝、ボクの誘いに集まったのは五匹の仲間だった。その子たちを連れて出掛けることにした。
「さあ、出発。」
今日は六匹の勇士たちが堂々と胸を張って並び、やつらの居る明るい場所へと向かった。
ボクらが近づいて来るのに気付いたのだろう、昨日のおばさんと小さい子たちが迎えに来てくれた。

|
|
第8話 おばさんのお話
|
|
「いらっしゃい、よく来たわね。」
おばさん達は、歓迎してくれた。
「お食事が来るまで、まだしばらく時間があるから、お話でもしましょう。」
おばさんは、色々とお話を聞かせてくれた。
ここに居るのは皆家族であること。
おばさんが子供の頃は、親は二匹しか居なかったのに、今では、こんなに家族が一杯になったこと。
「この子は、私の孫たちなのよ。あなた達もそうかしら。」
大人達は赤い色をしているけれど、小さい子は白く、成長と共に段々と赤くなっていくこと。
「あなた達も大きくなったら、きっと真っ赤なめだかになるのよ。」
季節というのがあって、これから暑くなっていき夏が来る、それが過ぎれば段々と寒くなり凍えるような冬が来ること。
「私の家族も始めての冬は、とても冷たくて、たくさんの子達が冬を越すことが出来なかったの。あの子達が生きていれば、もっと賑やかだったでしょうに。でもね、春が来れば男の子達は皆立派なヒレを広げて泳ぎ回るようになるのよ。それを見るのが楽しみだわ。来年は見ることができるかしら。」
僕達は、懐かしそうに語るおばさんの話を聞いて、想像を膨らませていた。
ボクは、一つだけ聞いてみた。
「何故、生まれたばかりの頃、僕達のような小さい子を襲って来たの?」
「そうだよ、自分の家族なのに。」と仲間も聞きたそうであった。
すると、おばさんは、
「ごめんなさいね。皆、憎くて襲っているわけではないの、家族が増えてくると食べるものが足りないのよ。食べられるものは何でも食べないと生きて行けないの。特に、子供達の育ち盛りの頃は体も大きくなるので、いつも、食べて体力を付けなければ泳ぐことが出来なくなるの。私たちは、泳ぐことが出来なくなれば、すぐに生きて行けなくなってしまうわ。あなた達も大きくなれば、きっと分かるでしょう。」
少し、沈黙が続いた。
「でも、生まれたばかりの子を襲わなくても良いだろうに。」とボクの一言だけで、
また、沈黙が続いた。
その時、いつものように食べ物が降ってきた。
「さあ、お上がりなさい。」
待ちくたびれて空腹の六匹は、一斉に食べ物に飛びついた。
小さな子達は、早く見つけて口にしなければ大きなやつが一気に食べ物を口に懸け込むので、少ししか食べられずに終わってしまう。
あっという間に水面の食べ物は食べ尽された。
「今回は少なかったわね。」
おばさんも、僕達に遠慮したのか、ほとんど食べられなかった様だった。
ボクは、おばさんの言った事が少し分かったような気がした。

|
|
第9話 上手な食べ方
|
|
小さい子たちが待つ住処へ帰った僕達は、おばさんに聞いた話を聞かせてあげた。
やつらが襲ってくる理由だけは、誰も話さなかったけれど。
小さい子達は、少し大きくなるまでは葉の陰に隠れて流れて来る食べ物を待つほうが良いけれど、少し大きくなれば皆が集まる所へ行っても大丈夫だから、大きい子グループと小さい子グループに分かれて行動すれば良いだろうと言うことになった。
その後、ボクは考えた。
もっと安心して、効率良く食べる方法は無いものだろうかと。
食べ物が降ってくる直前には、気配を感じた奴らは我先にと食事場所へ集まり、少しでも前へ行こうとしている。だから、ザワザワと音がするほど波立つのだ。
けれど、実際に食べ物が降ってくると、かなりの速さで広がって行く様に水面を漂うので、皆、食べ物を追うように後ずさりして散らばっていく。
一番前に居ても一瞬で食べ物は通り過ぎてしまうから、食べている間にほとんどが流れ去ってしまっている。ならば、初めから少し後ろの方で待っていても変わらないのではないか。
いや、待てよ、余り前に居るより、少し下がって食べ物が流れて来る方を見ながら待っていた方が、効率良く食べることが出来るはずだ。
そうだ、前の方で大きい奴らがひしめき合っている周りを、少し離れて囲むようにすれば、大きい子と小さい子が一緒でも食べ物は確実に食べられるだろう。
暗くなりかけていたが、皆に言っておこうと考えたボクは、明日の食べ物の食べ方を説明して回った。
翌日、大きい子グループは、奴らが集まっているところから少し離れた位置で前に出て、奴らの集まる方へ向かって横並びで食べ物を待った。小さい子グループは、その後ろに引っ付くようにしていた。
食事場所の中心に陣取ろうとザワザワしている奴らを尻目に、少し離れて近寄って来ない僕達を見て、おばさんは不思議そうな顔をしていた。
そのうちに、食べ物が降ってきた。
大騒ぎしている奴らを見ていると、間から次々と食べ物が流れ出てくる。水の流れと奴らのヒレの力で押された食べ物は非常に速く流れてきて、すぐに僕達の口先までやって来た。流れて来る方を正面から見ているので、皆、楽に口にすることが出来たし、小さい食べ物も沢山流れてきて、小さい子でも安心して食べられた。
「いい方法だったね。」
今日は、皆の満腹になった笑顔を見ながら、過ごした一日だった。

|
| 第10話 君の名は |
|
少し満足して寝床に付いたボクは、前から気になっていたことを思い出した。
やつらは皆、何と呼び合っているのだろう。
「そうだ、名前を聞いてみればいいんだ。待てよ、その前に自分の名前を付けなければ『ボクは**です。』って自己紹介できないなあ。何て名前にしようか。
ジョー、マリン、ペロッチー、パッパ、プウプウ、ペロペロ、ポワンポワン、・・・。
難しいなあ。」
半分、夢うつつになりながら考えていたら、
「ねえ、メドゥルノ、メドゥルノ・・・。」
と呼ばれた声に目が覚めた。
呼んでいたのは、最初に会った彼女だった。
「ボクは、メドゥルノなのかい・・・。ムニャムニャ。」
「何言ってるの。何時まで寝ているのって言っているのよ。」
「もうすぐ、食べ物が降ってくるわよ。今日は私も連れてって。」
現実の世界に戻ったボクは、
「分かったよ。皆で出かけよう。」
水面に上がった時には、既に食べ物がたくさん浮いていて、やつらは皆、食事の真っ最中であった。僕達も慌てて食事を済ませた。
「さあ、帰りましょ。」
と、彼女の声に、
「ちょっとボク、行きたい所があるから、皆を連れて先に帰っててよ。」
そう言って皆を先に帰し、やつらに名前を聞いて回ることにした。
ボクは、えーっと、「メドゥルノ」だ。
一番近くに居た大きいやつに、恐々声を掛けた。
「やあ。」
「何だい。」
「名前を教えてくれない?」
「名前なんて無いよ。」
メドゥルノは、
「エーッ。」
近くに居た他のおじさんにも、名前を聞いてみたら、
「名前って何だ?」
と、返って来た。
それから、近くにいた者に片っ端から声を掛けたけれど、
「名前なんて無いよ。」
「知らないな。」
と、ことごとく吊れない返事が返ってきた。
「ショック!」
聞きつかれたメドゥルノはガックリしながら、近くで鬼ごっこをして遊んでいる三匹の子達をぼんやりと眺めていた。
すると、メドゥルノが見ている事に気付いたのか、その子達はメドゥルノの方へ近づいてきた。
「やあ。」
「あっ、こんにちは。」
一匹の子が、
「初めて見る顔だね。何処から来たの。」
メドゥルノは、
「ああ、向こうの林の下からだよ。」
と、答えると、
「一緒に遊ばない?」と聞いてきた。
余り遊びたい気分ではなかったけれど、折角誘ってくれているのだからと思い、
「まあ、いいけど。」
と、気の無い返事をした。
次にその子が発した言葉に、メドゥルノは驚いた。
「ところで、君、何て名前なの?」
「エエーッ。皆、名前が無いんじゃないの?」
メドゥルノは、思わず聞き返した。
「そんなことないよ。」
三匹の子達は、それぞれを呼び合うために自分たちで名前を付けていたのだった。
「ボクは、ガー。」
「ボクは、アー。」
「ボクは、ビャー。」と、三匹は名乗った。
「ハハハハハ・・・。」
メドゥルノは思わず笑ってしまった。
「ごめん、ごめん、ボクの名前は・・・アレッ・・・えーっと・・・。」
しばらく考えて、いや、今日付けた自分の名前を思い起こして、
「そうそう、ボクは『メドゥルノ』というんだ。」
すると、ガーは、
「フーン。覚えにくい名前だね。」
メドゥルノは、
「君たちこそ、何故、そんな簡単な名前にしたの?」
「一言にした方が楽じゃないか。」
ガーは、そう言って、大きく口をあけて「アー。」と呼ぶと、アーが、
「こうやって口を開けるだけで、名前を呼べるじゃない?」
と言った。
「確かにそうだね。」
考えてみれば、あれやこれやと難しい名前を考えなくても、区別が付けばいいのだから、簡単な方が良いということか。
妙に納得させられた気分だった。
ガー、アー、ビャーの三匹と少し遊んで、ボクは林の向こうの住処へと帰った。
「また、遊ぼうね。」
「またねー。」

|
| 第11話 名前を付けたい |
|
やっぱり、名前で呼び合う方が良いなあと思ったボクは、次の日から皆に名前を付けて回ることにした。
まずは、彼女に問いかけた。
「名前を付けて回ろうと思うんだ。君は、何て名前がいい?」
すると、「名前って何?」と聞いてきた。
メドゥルノは、名前の意味も知らないんだと思いながらも、説明した。
「お互いを呼び合う時の言葉さ。ボクは『メドゥルノ』って付けたから、ボクを呼ぶ時は『メドゥルノ』って呼んでくれればいいんだよ。」
すると、彼女は、
「メドゥルノ。」
「何だい。」
「メドゥルノ。」
「何だってば。」
「メドゥルノ、メドゥルノ、メドゥルノ・・・わあ、面白い。」
「名前で遊ばないでくれよ。」
更に、彼女は聞いてきた。
「私は、何にすれば良いかしら。」
メドゥルノは、少しの間考えていたが、
「そうだな、君は目がパッチリしているから『パチリ』なんてどうだい。」
「いまいちね。」 ガクッ。
「じゃあ、瞳が綺麗だから『メキレイ』は、どうかなあ。」
彼女は、瞳が綺麗と言ったメドゥルノの言葉に眼を輝かせて、
「そうね、『ヒトミ』にするわ。」 ガクッ。
「結局、自分で決めるんじゃないか・・・ブツブツ。」と、メドゥルノは頭の中でぼやいて、
「ボクは今から名付けの旅に出るから、しばらくお別れだね。」
と格好良く決めようとしたら、
「面白そうだから私も行くわ。」
「・・・・・。」
結局は一人旅とは行かなくなり、ヒトミと一緒に名付けの旅へ出ることになった。
最初は大変だった。
出会った子に名前を尋ねても、無視されて名前を付けるところまで聞いてくれない。
「食事中だから。」
「今、忙しいから。」
挙句の果てに、同じ子に二回同じことを聞いて「またお前か。」と怒られたり。
やっと聞いてくれて名前を付けてあげることが出来て「やったあ。」と喜んだのに、
「では、あなたのお名前は?」
と聞き返すと、もう忘れていたりして。
苦労して、苦労して、やっと数匹のメダカに名前を付けたけれど、「あなたの名前は『***』ですよ。」と念を押しても、やっぱり、すぐに忘れてしまう。
ふたりは、疲れて、葉の上で休むことにした。
「やっぱり無理なのかなあ。」とメドゥルノがつぶやいたその時、昨日遊んだ三匹の子たちの内のひとりが通りかかった。
「やあ、『ガー』じゃないか。」とメドゥルノが声を掛けると、
「違うよ。ボクは『ビャー』だよ。」
「アー」はまん丸な体をしているので、すぐに区別が付くけれど、「ガー」と「ビャー」は良く似ていた。メドゥルノは、頭に黒いマークが有るか無いかで区別したつもりだった。
「頭に黒いマークのある方が『ガー』ではなかった?」
「違うよ、ボクは『ビャー』だよ。」
と言うから仕方が無い。ボクの覚え間違いだったんだ。
メドゥルノは、
「ところで、ボクの名前を覚えている?」
「覚えてないよ。」 ガクッ。
横に居て、ふたりの会話を聞いていたヒトミが、半分笑いながら話しかけた。
「そうなのよ。特長をそのまま名前にしないから忘れられるのよ。オチビやデブッチョなんて、名前を付けたわけじゃないのにそう呼んでるんだから。」
メドゥルノは、
「そうなのか。」と言って、浮き上がり、
「よし、もう一度やり直しだ。」
ふたりは、住処の近くへ戻って名前を付け直す様に進めることにした。
出会った子の特長を良く見て、覚えやすい名前を付けてあげるのだ。
「君は頭が丸いから『マル』という名前はどうかな?」
「『マル』なら分かりやすいね。それにするよ。」
また、別の子には、
「あなたは、背中に線が入っているから『セン』という名前が良いんじゃないかしら。」
「分かったよ。」
出会ったメダカたちの何匹かに名前を付けていくと、周りにいたメダカたちも、特長を見つけて名前を考えれば良いと分かったので、自分たちで名前を付け始めた。
進みだすと放って置いても名前付けは浸透していった。
メドゥルノは、その様子を見て、
「やっぱり、皆不便だと思っていたんだね。」と、つぶやいた。
安心したふたりは、住処へ戻って小さい子たちにも名前を付けることにした。

|
| 第12話 恐ろし谷 |
|
それから、しばらくは事件も無く、メドゥルノも出掛けて行っては食事をしたり、おしゃべりしたり、時にはガー、アー、ビャーの三匹と遊んだり、普通な日常を過ごした。
近くにいる仲間達の名前も随分覚えたし、行ったことの無い場所へも時々出掛けた。
多くのことを学んだメドゥルノは、体も大きくなり、スマートで強い少年になっていた。
ある日、ガー、アー、ビャーの三匹と遊んでいた時の事、アーが恐ろし谷の話を始めた。
「メドゥルノは、あの恐ろし谷へ行った事があるかい。」
と聞いてきた。
「何だ。それは。」
とメドゥルノが聞くと、アーは岩の方を見て言った。
「あの、大きな岩の向こう側を下へ降りていくと有るのだけど、誰も近づかないのさ。谷へ降りて左へ行けば、奥の方にここと同じような広い国があるんだけど、すごい番人が居て決して入ることが出来ないんだ。右へ行けば、見えない壁にぶつかるけれど、壁の向こうには想像も付かない程の大きな眼をギョロっとさせた化け物が行ったり来たりしているんだ。見えない壁越しに覗き込もうとすれば、向こうも馬鹿でかい目で睨んでくるんだ。体が震えて逃げて帰ってきたよ。」
メドゥルノは、疑うように、
「へエー、そんなところがあるのかい、面白そうだなあ。」
と、とんでもない返事をしたものだから、それではとばかりにガーが切り出した。
「鬼ごっこで負けたやつは、恐ろし谷へ行って何かを取って帰るというのはどうだい。」
アーは、「嫌だ。」と鬼ごっこから外れたが、強がりのメドゥルノは、
「よし、勝負だ。」
と参加してしまった。
そして案の定、負けてしまった。
負けたのだから仕方が無い、勇気を見せなければと思い、
「分かったよ、ボクが行って化け物を懲らしめてきてやるよ。」
と、口走ってしまったが、本当だったらどうしようと不安で一杯になった。
ガー、アー、ビャーの三匹も岩の上まで付いてきて同情したような目で見送ってくれた。
「頑張れよ。」
岩の上から見下ろすと、谷は深く急降下するように底の方まで掘り下げられていて、底にはごろごろと石が並んでいる。そして、石の周りを囲むように、メドゥルノの住処の周りにある林とは違う黒っぽい植物がこちらの方へ向かって茂っていて、その向こうは良く見えない。黒っぽい植物の葉は細く尖っていて密集しており、水が流れるのに揺れて近づくと刺さりそうである。
谷底の奥の方に少しだけ林の切れている所があるので、そこから向こう側へ抜けようと目標を定めた。
「エイ、ママよ。」
メドゥルノは、一気に谷底へ駆け下り林の切れ目を抜けた。
抜けた先は、明るくて真っ青な世界だった。
左の方を見ると、奥は丘のようになっており、確かに丘の上のその先には広い空間が有るようで、たくさんの影が動いている。まるで、メドゥルノが産まれた時に最初に見た景色と同じようであった。
そちらへ向かおうと左の方へ行くと、アーが言っていた通り番人が現れた。
「通してください。」
とメドゥルノはやさしく言った。
けれど、番人は何も言わない。
「ならば、通るぞ。」
と、横を通ろうとすると番人は目の前へ寄って睨んでくる。左へ動くと左へ寄ってくる、右へ動くと右へ寄ってくる。まるでメドゥルノの動きを知っているかのようにピッタリと付いて来て離れようとしない。
「アーの言っていた通りだ。すごい番人だ。」
しばらく睨み合いを繰り返したが埒が明かないと思ったメドゥルノは、諦めて右の方へ行くことにした。
そこには、果てまで続いているのではないかと思うほど広大な空間が広がっていた。
「ワァー、凄い。」
思わず叫んだメドゥルノは、喜んで、その空間へ飛び出そうとしたが、見えない壁に鼻を強打してしまった。
「イターイ。」
あまりの景色に感動して、アーが言っていた見えない壁のことをすっかり忘れていた。
「ここは、絶対に抜けてやるぞ。」
とばかりに、突いて押して、尻尾で叩いて、果ては体当たりまでしてみたものの、壁はびくともしなかった。
壁を抜けることばかりに熱中していたメドゥルノは、辺りが急に暗くなったことに気付かなかった。ふと、壁の向こうを見るとさっきまで広がっていた広大な空間が見えない。
「もしかして。」
悪い予感を感じたメドゥルノは、恐る恐る、壁の斜め上を見上げて絶叫した。
「ギャー。」
そこには、でかい眼をギョロつかせ、鼻の下に髭を一杯蓄えた化け物が、今にも襲わんとばかりに見下ろしていたのだ。
メドゥルノは、慌てふためいて林の間を抜け、岩にぶつかりそうになりながら逃げ帰り、住処に着くなり岩の間へ潜り込んだ。
住処の近くにいた仲間達は、驚いた顔で見ていたが、
「何も聞かないでくれェー。」
と言って、岩の間から出て行けなかった。
すると、アーが近寄ってきて、
「言ったとおりだろう・・・。」
と低い声を響かせたので、アーを見ると、突然、アーが化け物に化けて迫ってくる。
「ギャー。」
「ハッ。夢か。」
アーの化け物は夢だったけれど、
「夢にまで出てくるなんて。」
その夜、メドゥルノは一睡も出来なかった。

|
| 第13話 夏が来る |
|
恐ろし谷の事があって以来、メドゥルノは少し元気を無くしていた。
「ああ、情けない。アー達の顔が見れないよ。」
食事に出掛けてもサッサと食べ終えると、住処に戻ってじっとしているのが日課のようであった。
それに、何か体が熱くて動く気になれない。
メドゥルノは、あの時のショックで熱が冷めないのだろう、このまま高熱で天に召されるのかもしれないとさえ考えるようになっていた。
そんなある日、涼しい波が自分の体に向けて流れて来るのを感じた。
ふと見上げると、大きなヒレで水を動かしているメダカの姿があった。
「アッ、あの時のおばさん。」
それは、メドゥルノが小さい頃、食事に招待してくれて、色々な話を聞かせてくれたおばさんだった。
「あなたがメドゥルノだったのね。」と話しかけられたメドゥルノは、
「何故、ボクの名前を知っているの?」と聞くと、おばさんは、
「ええ、皆、知っているわ。私達の家族皆に名前を付けて回っていたんだってね。大人たちが誰も出来なかった事を、小さな子が実現してくれたって、皆、喜んでいるのよ。」
「そうだったんだ。それじゃ、おばさんは何という名前を付けたの?」と聞くと、
「私は、あなたに会う前から名前があったのよ。アンドリューと呼んでちょうだい。よろしくね。」
メドゥルノは、
「アンドリューおばさん。」
「なあに、メドゥルノ。」
「見舞いに来てくれてありがとう。」
すると、アンドリューは、
「ホホホホッ・・・、見舞いに来たわけじゃないのよ。」
「・・・・。」
「周りを見て御覧なさい、あなたの仲間たちも元気が無いでしょう?」
と言われて、メドゥルノは始めて周りを見渡した。
何匹かの仲間たちが底に引っ付いてハアハアと息遣いが荒いようだ。
アンドリューは続けた。
「暑くて動けないのは、あなただけじゃないの。いつか話さなかったかしら、もう夏が来ているのね。まだ、暫くはこんな暑い日が続くのよ。皆で助け合って乗り越えないとね。」
それを聞いたメドゥルノは、自分のことばかりで仲間を忘れていたことに気付いた。
「分かったよ、アンドリューおばさん。でも、ボクは何をすればいいの?」
「そうね、暑いときは日差しを避けて物陰に居るのが良いわね。それから、水がゆっくりと流れているところで、こうして胸ビレで水を掛くのよ。水を回していると温まった水を動かして少しずつ涼しくなるのよ。あなたなら、もっと良い方法を見つけられるかもしれないけれどね。」
アンドリューおばさんは、大きなヒレを動かしながら話した。そして、遠くの方を見ながら話を続けた。
「そう言えば昨年は暑い夏だったわね。食事の時以外は皆で集まって水を掛け合ったりして凌いでいたのに、我慢できなかったのね、水面を飛び跳ねて姿を消してしまった子もいたし、真っ直ぐに泳げなくなったり、食べ物を口にすることも出来なくなった子もいたの。そういう子はすごく痩せて生き残ることが出来なかった。皆、大切な友達だったのに。」
聞いていたメドゥルノは、
「夏って大変なんだね。ありがとう教えてくれて、少し元気が出た気がするよ。どうすれば涼しく過ごすことが出来るか考えてみるよ。」と答えた。
アンドリューおばさんは、
「そうね、今年は涼しければ良いのだけれど。」
と言いながら、ゆったりとした泳ぎで、ゆっくりと自分の住処へと帰っていった。
次の日、メドゥルノは、少しずつ移動しながら一番涼しいと思われる場所を探すことにした。
石底の上をササッと動き「ウーン。」、またササッと動き「ウーン。」、明るいところへ出ると「アチィー。」、すぐに陰に入って「ウーン。」、とやっていると、後ろで同じように何かが動いていることに気付いた。
サッ(ササッ)、サササッ(サササッ)、ササッササッ(ササッササッ)。
メドゥルノは気になって、進む振りをしながら振り向いた。
そこには頭があって「ゴツン。」
「ウワーッ。」と、メドゥルノも後ろにいた者も驚いてずっこけた。
「何だ、オチビじゃないか。驚かすなよ。」とメドゥルノの声に、
「気付かれたか。何をしているのかと思って、付いて来たんだ。」
オチビは、おかしな行動をしているメドゥルノを見て、何をしているのかと思ったのだった。
「暑くて倒れそうだろう。だから、少しでも涼しいところを探そうと思って、少しずつ動いて探っているんだよ。」
とメドゥルノは説明して、
「それにしても、オチビは元気そうだね。」と聞くと、
「それなら、ボクがいつも居るところが一番涼しいよ。ボクは、いつもそこに居るから暑さなんてへっちゃらさ。」
と言って、案内してくれた。
オチビはとっくに涼しいところを探して、移動していたようだ。
その場所へは、今の住処を出て、いつも食事をするところへ行くまでの間にある林が、丁度、途切れている細い隙間を降りて行くのだった。うっそうとした林が日差しを遮り、岩の裂け目が幾つか有って、裂け目からは冷たい水が噴出していた。
そこには、ヒトミとデブッチョも休みに来ていたようだ。
オチビが、
「お客さんを連れてきたよ。」
メドゥルノは、
「やあ、こんにちは。」と言いながら、付いて入った。
ヒトミとデブッチョは驚いたように、
「あらっ、こんにちは。」
「やあ。」
そこで、メドゥルノは、
「ここは、涼しいね。こんなところがあったんだ。皆も呼んであげようよ。」
と言うと、ヒトミが答えた。
「ここは狭いので、オチビみたいに小さい子は良いけど、大きい子が五匹も入れば一杯になって窒息しちゃうわよ。」
「でも、あの暑い住処の辺りにずっと居れば、皆、動けなくなってしまうんじゃないかな。」
メドゥルノは、辺りを見回しながら考えていた。
岩の裂け目から噴出した涼しい水は、密集した林にぶつかり向きを変えて上の方へ流れて行く。林の上へ流れ出た水は、上の暖かい水にぶつかって、また、下へ戻って来ている様だった。
「だから、ここだけが特に涼しいんだ。」
と独り言を言って、林の中へ頭を突っ込んだ。
メドゥルノが林を掻き分け掻き分け進んでいくと、出来た隙間に、後を追うように涼しい水が吸い込まれていく。
暫くして、呆れ顔で見ていたヒトミたちの前に、体に葉のかけらを一杯付けたメドゥルノが戻ってきた。
「フウー。もう一回。」
と言って、また林の中へ飛び込んだかと思うと、暫くして戻ってきた。
戻って来るなり、緊張気味にこう言った。
「この林の向こうは僕達の住処なんだね。涼しい水は林に堰き止められてしまうから、住処の方へは温められた水しか流れていかないんだ。」
「どうすれば良いの。」と、ヒトミが聞くと、
「こうすれば良いのさ。」
と言って、メドゥルノは、また林に飛び込み、林から頭だけを出した。
「こうして、林に隙間を作って行って、皆のヒレで水を送り込めば、涼しい水が住処の方へ流れるようになるだろう。」
それを聞いていたヒトミは、一番に「やってみましょ。」と乗り気になったかと思うと、
「仲間を呼んでくる。」と言うなり、呆気に取られているメドゥルノたちを尻目に飛び出していった。
オチビやデブッチョ達も、「手伝うよ。」と言ってくれた。
「それでは、皆で林に穴を開けよう。」
そろって林の中へ飛び込んだ。
でも、オチビは小さすぎて枝と枝の細い隙間をスルッと抜け出てしまい、全く隙間が広がらない。一方、デブッチョは頭を隙間に突っ込んだまま進むことも戻ることも出来ずアップアップしていた。
「僕たちだけでは穴を開けるのなんて無理だよ。」
と言って、頑丈な枝が絡み合った林を見ていた。
「もっと手伝いの数を集めて、何匹かで一斉にぶつかっていかないと、水が流れ出すだけの穴は出来ないだろう。ヒトミを待つことにしよう。」
とメドゥルノが言った時、
「そうだねー。」と言いながら、メドゥルノの背後に近づいてくる者が居た。
そして、林の方を眺めているメドゥルノの真横に並んできた。
メドゥルノは、横を見るなり、
「ギャー、ボクを食べないで。」と叫んで、転んだ。
というのも、メドゥルノの横には、メドゥルノの頭ほどもありそうな大きな眼と水を吸い込めばメドゥルノも一緒に吸い込まれそうなほど大きい口が有ったからだった。
さらに、後ろへ目を向けると、赤くて高くて長い体が後ろの方へ伸びていて、狭い空間に入りきらず、尻尾やヒレは皆の上に覆いかぶさっていた。
メドゥルノは、体が震えて動けなくなった。
すると、その者のヒレの上から、
「お待たせー。」というヒトミの声が聞こえた。
「私の友達のおじさんを連れて来たわよ。ここでは、一番の力持ちで怖がられているんだって。でも、物静かで優しいおじさんなの、私は大好きよ。」
そのおじさんは、大きな口を開けて、口の大きさに似合わない様な小声で話した。
「ボクの名前は『チカラモチ』って言うんだ。ヒトミちゃんに付けてもらった名前だよ。」
メドゥルノは、ほっと一息ついて、
「良い名前だね。」
と、見たままじゃないかと思いながらも、笑って答えた。
チカラモチおじさんは、
「メドゥルノが大変だとヒトミちゃんに聞いたものだから、助けに来たんだけど大丈夫そうだね。」
と言って帰ろうとしたので、メドゥルノは慌てて、
「チカラモチおじさん、大変なんだ。」と引き止めた。
それから、自分の住処の近くに居る仲間が暑くてまいっていることや、涼しい水を送るために林に隙間を作って穴を開けたいのに出来なくて困っていることなど、詳しく説明した。
スウスウと大きな息をしながら聞いていたチカラモチおじさんは、
「分かったよ、皆、危ないから後ろへ行ってなさい。」
と言うなり、その大きな体を揺さぶりながら林へ向かって突進していった。
「スゴーイ。」
唖然として見ていた皆が、驚いて声を上げた。
チカラモチおじさんが通り抜けた後は、そこがうっそうとした林であったことを疑うほどに綺麗に枝が切り取られ、こちらの涼しい流れにぶつかるように、温かい水が流れ込んできた。
メドゥルノの、
「皆、水を扇ぐんだ。」
の掛け声に、傍に居た仲間たちが揃って涼しい水を送るように胸ビレを動かした。
最初は逆流して流れ込んで来た温かい水も、次第に流れがゆるくなり、少しずつ涼しい水が住処の方へ流れて行くようになった。
そこへ、ぐるりと回って反対から戻ってきたチカラモチおじさんが、最後の一掻きを大きな胸ビレで行うと、皆、その勢いに乗って、住処の方へ一緒に流された。
そして、「じゃあまたな。」と一言残して、ヒトミと共に帰って行った。
「チカラモチおじさん、ありがとう。」皆は、笑顔で見送った。
同時に、メドゥルノにとっては、それは、赤い大きなやつらが襲ってくるという恐怖を拭い去ることになった出来事でもあった。

|
| 第14話 家族を助けろ |
|
メドゥルノたちの活躍で少しは涼しくなった住処だったが、それでも、暑い夏は容赦なく皆の体に迫ってきた。日中は岩陰に集まって、お互いを扇ぎあいながら過ごし、朝早くの涼しい間に水面へ出て食事する日々が続いた。
暑さのせいだろう、食事場所に来るメダカたちも少しずつ減ってきていた。
そんなある日のこと、メドゥルノ達の住処に大きなお客さんが訪れ、住処に着くなり横に倒れこんだ。
メドゥルノは、その客の顔を見て叫んだ。
「アンドリューおばさん。」
駆け寄ったメドゥルノに、アンドリューおばさんは弱々しい声で話した。
「お願いがあるの。私達の家族を助けてあげて。」
「何があったの?」
問いかけるメドゥルノの元気な姿に、アンドリューは少し落ちついたのか、起き上がって話を続けた。
「今年も暑い日が続いて、大人たちは元気が無くなっているのは仕方が無いわねえ、もう歳だもの。でも、若い子達も大人に混じってじっとしてしまっているのよ。本当は、私達大人が教えてあげないといけないのに、暑さを避ける方法を知らずに居るのね。私もこんな状態なのだから。」
メドゥルノは、全てを聞かなくても理解できた。
「分かったよ、アンドリューおばさん。おばさんに教えてもらったことや、チカラモチおじさんに手伝ってもらったおかげで、僕達は無事で居られるのだから。今度は、僕達が助ける番だよ。」
メドゥルノは、住処の仲間達の中から大きい子達を集めて、アンドリューおばさん達の住処へ見に行くことにした。
そこは、いつも食事をする場所を越えて、恐ろし谷を横目に、さらに林を超えた所にある。一行は周囲に危険が無いか注意しながら向かって行った。
食事場所を過ぎた辺りから、水は淀み始め、メドゥルノ達の体も熱くなってくるのだった。さらに、奥の林を抜けると、水は濁り、生暖かい流れが林に沿って巻くように、ゆっくりと動いている。
「皆、こんな所で我慢して過ごしているのだろうか?」
一行は口を塞ぎながら、下の方へ降りて行った。すると、どうだろう、大きな大人達に混じって、メドゥルノと変わらないくらいの小さな子達も、皆、底に沈んでじっとしている。
中には、横倒しになり、腹を見せている者もいた。
「何てことだ。」
メドゥルノとヒトミは、その中にチカラモチおじさんを見つけて、慌てて駆け寄った。
「大丈夫ですか、おじさん。」
チカラモチおじさんは、元気の無い声で、
「ボクは大丈夫だから、小さい子たちを助けてやっておくれ。皆、暑さで動けなくなっているんだ。」
メドゥルノ達は、何匹かずつに分かれて倒れている子達を引き上げようとしたが、持ち上げることさえ出来なかった。自分でヒレを動かすことさえ出来なくなっている子達を、引き上げることなど、とても無理だと思った。
「どうすれば良いんだ。」
皆、必死だった。
メドゥルノも、体が重くなり動きにくくなってきた。
「このままでは、自分達もやられてしまう。」
一行は一端、上にあがって方法を考えることにした。
「早くしないと、皆、死んでしまうよ。」
「良い方法が無いのだろうか。」
相談している中で、一行に加わっていた仲間のオトナシが言った。
「メダカを動かせないのだから、水を動かすのはどうだろう。」
一行は、オトナシの方を見て、驚いた。
オトナシは、いつも後ろの方に居て何もしゃべらない静かな子だったからだ。
「どうすれば、水が動かせると思う。」
と、メドゥルノの問いかけに、オトナシが答えた。
「自分達の住処には涼しい水が流れて来ているのだから、きっと、この辺りにも流れがある筈だよ。おそらく、向きが違うからこの辺りへ来ないんだよ。」
メドゥルノはそれを聞いて、
「よし、調べてみよう。」と高いところを目指して進み始めた。
一行も、揃って後を追い、周囲を見て回った。
左の方は、恐ろし谷の手前にある大きな岩がすぐ近くまで並んでおり、岩が終わる所から先へは、恐ろし谷と同じ様に尖った葉の林が密集して奥の方まで囲むように続いている。右のほうは、岩がさらに高く登っていて奥の林まで続いている。
「完全に囲まれているではないか。」
涼しい流れは、恐ろし谷を駆け上ってきて、こちらへは降りずに食事場所の横から、メドゥルノ達の住処の方へ流れている。
メドゥルノはそれを見て、
「ハッ!」と感づいた。
「自分達の住処の方へ涼しい水を流すように林を切り取ったから、こちらへ流れて来なくなったんだ。どうすれば良いんだ。早くしないと。」
気ばかりが焦って手段が見つからない。
オロオロしている一行の所へ、ユラユラとアンドリューおばさんが戻ってきた。
「少し楽になったので様子を見に来たのだけれど、やっぱり無理なのかねえ。」
「そんなことは無いよ、絶対に助かるから。」
メドゥルノは強がって見せたが、内心、途方にくれていた。
その時、オトナシが突然駆け出して、恐ろし谷の手前の大きな岩に登り始めた。すると、急な流れに流され、尖った葉が生い茂る林の中へ滑り落ちた。
「大変だ! オトナシが危ない。」
皆、叫んで助けに行こうとしたら、オトナシは平気な顔をして上がってきた。
「この林の尖った葉は柔らかいんだ。それに、岩の上にはあんなに強い流れが起きているんだ。」と言うオトナシの言葉に、
「そうだ。そうだよ、あの尖った葉を取り去って流れをこちらへ向けてやれば、下の方へ流れ込むようになるかもしれない。」
一行は、岩の上へ登った。
そこには、冷たいほどの急な流れが密集した林の上を通り過ぎており、皆、ヒレを広げただけで林の上に流された。
「頑張って、葉を削り取るんだ。」
メドゥルノの声に、一行は無心に葉を口に銜えて引っ張った。
ちぎれた葉は、強い流れに乗って林の上を舞って行き、舞い上がった葉は奥のほうに集まって積みあがっていく。
一行は、力の続く限り、葉を削り続けた。
次第に一行が葉を抜いた部分の林は背が低くなり、流れた葉のかけらは林の奥で山のように積もった。林の上を通り過ぎていた流れは、積もった葉にぶつかって下の方に向きを変えると、林を削り続ける一行の所へ温かい水が上がってきて大きな渦巻きになった。
「皆、逃げろ。」
メドゥルノの声に、一行は削るのをやめて、低くなった林の中へ潜り込んだ。
上を通り過ぎていた流れは、低くなった林からどんどん下へ流れ込み、岩に沿って上がってきては、一周ぐるりと巻いて、メドゥルノ達の住処の方へと流れていく。
暫くして、流れは緩やかになり、少しずつ下の方が見えるようになってきた。
どうなったのかも分からないままに林から出てきた一行は、ずっと、下の方を見ていた。
「皆、生きているだろうか。」
メドゥルノがつぶやいた時、一匹の大きなメダカがヨタヨタと浮き上がってきた。
「アッ。チカラモチおじさんだ。」
一行の前にやってきたおじさんは、一言、
「何てことをしてくれるんだ。」
その言葉がショックで声も出なかった一行に、
「おかげで、皆、助かったよ。」と、おじさんは笑った。
すると、下の方から次々と赤いメダカ達が浮き上がってきた。
アンドリューおばさんは、
「皆、助かったのね。ありがとう。良かった。」
その後、チカラモチ達も加わり、皆で、一行が削って低くなった林の一部を取り去り、流れが下へ行くようにした。
大所帯の家族達も無事、夏を乗り切れそうだ。
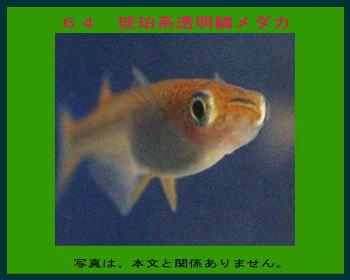
|
| 第15話 君の居場所 |
|
アンドリューおばさんが言うには、今年も暑い夏だとの事であったが、水が大きく流れるようにしたことや、子供達が慣れてきたこともあり、無事に平穏な生活が続けられた。
メドゥルノ達の住処では、夏が来るまでは毎日のように新しい子が加わり、世話を続けるヒトミを悩ませていたが、最近は、新しい子が加わることも無く、成長した子達は次々とヒトミの元を離れて行き、今では、ヒトミの後ろについて泳ぐ子も二匹だけになった。
アンドリューおばさんが最近のヒトミの様子を見ていて心配していたのを思い出したメドゥルノは、
「やあ、ヒトミちゃん、そろそろお世話係も卒業だね。」と、声を掛けてみた。
けれども、ヒトミは寂しそうに、
「小さい時は、皆、引っ付いてきて『おねえさん。おねえさん。』って行ってくれたのに、近頃は相手にもしてくれないんだから。」と言った。
「ハハハ。何、おばあさんみたいなことを言ってるんだ。」
気遣って声を掛けたつもりだったが、ヒトミには伝わらなかった様で、
「メドゥルノには分からないのよ。」
と言って、行ってしまった。
その日、ヒトミは夜になっても住処へ帰ってこなかった。
次の日の朝、いつもヒトミが連れている二匹の子がメドゥルノの所へやってきて、
「おねえちゃんが帰ってこない。」と、言うのだった。
困った様子の二匹を見て、メドゥルノは、
「おにいちゃんが捜してくるから待って居ろよ。」と、言い残して捜しに出掛けた。
メドゥルノは、以前ヒトミが世話をしていた子達の所へ順に聞いて回っていた。
「やあ、ヒトミ来なかった?」
「昨日、来たけれど、少しだけ話をしてすぐにあっちへ行ってしまったよ。」
その子が指す方へ行くと、別の子に出会った。
「やあ、君もヒトミが世話していた子だね。」と聞くと、
「アッ、メドゥルノおにいちゃん。久しぶりだね。」と元気そうだった。
「ところで、ヒトミ来なかった?」
「昨日、来たけれど、少しだけ話をしてすぐにあっちへ行ってしまったよ。」
「また、あっちか。」と、メドゥルノは出会った子の指す方へ行く度、ヒトミが世話をしていた子に出会い、ヒトミが訪れたかを聞いた。
もう、十匹程の子に聞いただろうか、知らない間にアンドリューおばさんやチカラモチおじさん達の住処の近くまで来てしまった。
「折角だから、おばさんの様子も見て行こう。」と思い、メドゥルノはアンドリューおばさんを訪ねた。
アンドリューおばさんは、メドゥルノを見て、目を丸くした。
「あらあ、どうしたのかしら。昨日はヒトミちゃんで、今日は、メドゥルノが来るなんて。」
「そうか、ヒトミはアンドリューおばさんの所へも来たんだ。」
メドゥルノは、昨日あったことや、昨日からヒトミが帰ってこないこと、それで気になって捜しに来たことなどを説明した。
アンドリューおばさんは、
「そうだったの。メドゥルノは優しい子ね。」と言って、昨日ヒトミが訪れた時のことを話してくれた。
「そうそう、寝床の掃除をしていた時だったわ、今にも泣き出しそうな顔をして私の方を見ていたの。話を聞いてみたら、小さい時に世話をした子達に会って回ったのだとか言ってたねえ。でも、誰も親身になって話を聞いてくれなかったみたいね。『恩知らず』なんて言ってたもの。『皆、自分達が生きることに忙しいのよ。』って話をしたけれど、丁度、別のお客さんがあったもので、十分に相手が出来なかったものだから、気付いた時にはもう居なくなってて、メドゥルノ達の所へ帰っていったと思ったのだけど、心配だねえ。」
メドゥルノは、
「ボク、もう一度捜してみるよ。」と言うと、
「私も一緒に行くわ。」と、付き合ってくれた。
メドゥルノとアンドリューは、ヒトミが行きそうな所を覗いてみたり、出会った子に聞いたり、必死で捜し回った。
ふたりは、心当たりを全て見て回ったが、ヒトミは見つからなかった。
「住処にも帰っていないし、途中、全部見て回ったのに見付からないなんて、一体、何処へ行ってしまったんだ。」と、メドゥルノの投げやりな態度で、アンドリューを困らせた。
「絶対、何処かに居るわよ。」とたしなめたアンドリューは、ふと、昔のことを思い起こしていた。
「そう言えば、私も小さい頃は良くあの岩陰で泣いていたわ。あそこから見ると谷を隔てた山の先まで、遠くの方が見渡せて心が落ち着くのよ。」とアンドリューの住処の向こう側にある大きな岩を見て話した。
「そこは、何処にあるの?」と、メドゥルノが聞くと、
「話したことが無いから、ヒトミちゃんも知らないと思うけれど。」とは言ったが、
「とりあえず行ってみようよ。」の言葉に、アンドリューは岩陰の所へ案内してくれた。
そこには、近付いて来たふたりに見付からない様にと、岩陰に潜り込むヒトミの姿があった。
この辺りを良く知っているアンドリューは、細かく岩陰を覗き込み、隠れているヒトミを見つけた。
「ここに居たの。と言うことは、あの時、小さくて泣きじゃくっていた時に、この場所のことを話してあげた子は、ヒトミちゃんだったのね。」
ヒトミは、ここならば誰にも見付からないだろうと思い隠れていたのだった。
アンドリューは、続けた。
「もう気が治まったかしら。メドゥルノに謝らないとね。ここから見ていたのだから、メドゥルノがどれだけあなたのことを捜していたのか、見ていたわよね。そう言えば、私の小さい頃の話をしたことがあったわね。つらいことがあると、いつもここで見ていたら、必ず誰かが心配して捜しに来てくれた。たとえ一匹でも私のことを思ってくれる子がいるから、私は生きて来られたのだと思うの。その子の為に生きようと思えたのよ。それがあったから、いつか自分の子を大切に守ってあげなければという気持ちになれたと思うの。だから、今はこんな大家族になって平和に過ごしていられるのよ。」
「あなたと一緒だった子達は、皆旅立って行ったのよ。それは、あなたのおかげだと言う事を誰も忘れていないと思うの。あなたも、もう少しすれば親になるのよ。今度は、自分の子を守ってあげなければならないの、思い出に浸ってなんて居られないわね。」
その時、遠くの方から、
「ヒトミさーん。ヒトミさーん。」と叫ぶ声がしてきて、段々大きく近づいてきた。
ここから見ると、声の主達が良く見えた。
「アア、皆。」と、ヒトミが叫んだ。
小さい頃、ヒトミが世話していた子達が、皆で捜していたのだった。
慌てて飛び出したヒトミを見つけた子達は集まってきた。
中には、今もヒトミが世話をしている二匹の子もいた。
「無事で良かった。」
「ごめんね、力になってあげられなくて。」
「私達は皆、ヒトミさんに感謝しているよ。」
「当然だろ。」
皆、口々に、思いを語っていた。
それを聞いて、ヒトミは、
「私こそ、皆に心配を掛けてごめんね。」と言って、皆の中へ飛び込んだ。
「良かった。」
ヒトミ達が寄り添って帰っていく後姿を、見えなくなるまで眺めていたメドゥルノとアンドリューだった。

|
| 第16話 おかしなやつ |
|
季節は、いつの間にか夏から秋へと移り変わろうとしていた。
真夏の暑さに元気を無くしていたメダカ達も、活気を取り戻し盛んに泳ぎ回るようになっていた。
そして、メドゥルノ達も、もう立派な青年になり、皆に混じって泳ぎ回った。
しかし、此の頃、辺りにおかしなやつが出るという噂が広がり始めていた。
そいつは、誰とは無しに体を突いてくるらしく、オチビは出会いがしらに強く突かれた様で、脇腹が傷つき、鱗も少し剥がれたのだった。
ヒトミも、目撃して、
「怖いわね。男女関係無く、手当たり次第に突いて来るんだから。」と不安な様子だった。
そう話している時に、突然ガーが飛び込んできて、
「少し、かくまってくれ。」と、息を荒げて、メドゥルノの後ろへ隠れようとした。
「どうしたんだ。」とメドゥルノが聞くと、
「やつが出たんだ。」と、ガーは震えて話を始めた。
「少し涼しくなったから、アーと一緒にメドゥルノ達の様子を見に行こうと出かけたんだ。メドゥルノ達の住処の近くまで来た時、いきなり横からやつが突進して来たんだ。」
そいつは、ガーがうまくかわしたので、その場で向きを変えて、今度はアーの方へ突っ込んできた。アーは体が丸くて泳ぎが苦手なものだから、腹の横に頭がぶつかり引っくり返りそうになったのだ。アーが危ないと思ったガーは、そいつの気を引くために、わざと目の前を横切って自分を追いかけさせたのだが、そいつの方が泳ぐのが速くて尻尾や背ビレを突いてくるので、死に物狂いで逃げてきたのだった。
「また、アーの方へ戻ったりしていないだろうなあ。アーが心配だ。」
それを聞いたメドゥルノは、
「ボク、見に行ってくるよ。」と言って、アーとヒトミを残して出て行った。
アーが、
「あいつ、勇気があるなあ。」と感心したが、
ヒトミは、
「メドゥルノは、いつも無謀なのよ。」
と、呆れた様子でメドゥルノが泳いでいくのを見ていた。
メドゥルノは、ガーが言っていた辺りを捜していた。
岩陰に居たアーを見つけたメドゥルノは急いで駆け寄り、
「大丈夫か。」と声を掛けた。
アーは、岩の間に頭を突っ込んだままで、
「寄るなー。あっちへ行け。」と、震えながら叫んでいる。
けれども、アーの丸い体は隠れていないので、簡単に分かったのだ。
「アー、ボクだよ、メドゥルノだよ。それじゃ、頭隠して尻隠さずだ。変なやつは何処かへ行ってしまったみたいだから、出ておいでよ。」
アーは安心した様子で、フラフラと出て来て、
「フウ、ビックリしたよ。いきなり突いてきたから避け切れ無かったよ。でも、こんな時は体が丸いと良いね。ぶつかろうとしても勝手に体が回ってしまうから、まともには当たらないんだね。」
「何言ってんだか。」
メドゥルノは、アーのとぼけ振りに安心した。
「アーの家まで送って行くよ。」
と言って、メドゥルノが浮き上ろうとした時、横からぶつかって来ようとする者が現れた。
アーが、「あいつだ。」と叫んだ。
瞬間、メドゥルノは、ヒョイと突っ込んできた者をかわした。
「さすがー。」
とアーが感心している傍から、そいつは、クルリと向きを変えて、また、メドゥルノの方へ突っ込んで来ようとした。
メドゥルノは大声で、
「何者だ、名を名乗れ。」と叫ぶと、
そいつは驚いたように立ち止まり、
「オレはシズカだ。」と答えた。
「シズカ、えっ、シズカじゃないか。ボクだよ、ボク、メドゥルノだよ。」
ふたりは知り合いだった。というより、メドゥルノが小さい頃に名づけの旅に出た旅先で知り合った子で、引っ込み思案で、いつも黙って誰かの後ろにくっ付いていたので、シズカと名付けたのだった。
「元気だったか、ちっとも見ないなあと思っていたんだよ。」
たちまち打ち解けたふたりは、懐かしそうに話を始めた。
シズカは、何をやっても周りの子に勝てなかったものだから、いつも目立たないように泳ぎ、誰かが近づいてくれば隠れるようになってしまった。でも、この前、たった一匹だけ出来た女の子の友達を、通り掛かった大きなメダカに連れ去られてから、取り戻すことを決心して、闘いの練習をしながら捜しているとのことだった。
「そうなんだ。大変だったんだね。」と話を聞いていたメドゥルノだったけれど、
「でも、誰ともなしに突いてくるのは良くないよ。」と言うと、
「だって、先手で行かないと勝てないだろう。」と答えてきた。
メドゥルノは、シズカがいきなり突いて来た訳が分かったけれど、
「そんなこと無いよ、堂々と名乗ってから闘っても十分に勝てるぐらい、君は強いと思うよ。見てごらん、周りの皆が怖がっているじゃないか。敵が来た時にだけ力を出せば良いんじゃないかな。シズカは、おとなしくて優しい子だったけれど、本当は強い子なんだとボクはずっと思っていたんだ。」
メドゥルノの言葉に、シズカは、
「分かったよ。」と納得してくれた様だった。
ふたりは、アーを連れて、アー達の住処へと向かった。
途中で、アーは小声で話し掛けて来た。
「実は、ボク、シズカが言っていたやつを知っているよ。たぶん、ハヤブの事だろう。」
それを聞いたシズカは、
「えっ、知っているのか?」と尋ねてきた。
アーは、いつもハヤブが居る場所を教えてくれた。
それを聞いたメドゥルノとシズカは、アーを住処へ送った後、ふたりで行ってみることにした。
そこは、恐ろし谷の横に有る岩を、反対方向へ下りて行き、暗い林を通り抜けた先だった。
「こんな所、来たこと無いよね。」
「アーは良く来ているのかなあ?」
と、ふたりは不思議そうに話しながら林を抜けた。
そこには、数匹の女の子に混じって、シズカの女友達の子もいた。
周りを、大きなメダカが一匹、行き来して女の子達の所へ近づき、また離れては近づきを繰り返していた。
何て奴だ、皆嫌がっているじゃないか、と思ったメドゥルノとシズカは、懲らしめてやろうと近付いて行った。
ところが、シズカは急に怖くなったのか、メドゥルノの後ろに隠れて、
「やっぱり駄目だ。」と弱気な声を出した。
行くに行けず戻るに戻れない状態のメドゥルノに、気付いたハヤブが駆け寄ってきた。
メドゥルノは、近付いて来たハヤブを見て、自分より遥かに大きいと思われる体に驚き、こいつと闘わなければならないのかと思うと恐怖心が先に出てくるのを抑えながら、
「やあ、ボクはメドゥルノ。」と、ちょっと逃げ腰で言うと、
「何か用か?」と、ハヤブが聞いてきた。
「あそこに居る女の子は、ボクの後ろに居るシズカの友達なんだ。返してくれないか。」
と震えながら頼んだ。
すると、ハヤブは、
「面白い。返して欲しければ、力づくで取り返すんだな。」と睨んでくる。
「何を。」と睨み返したメドゥルノだったが、余りに迫力が違い過ぎたのか、
「ハハハハハッ。」と、大笑いされた。
「オレは、お前に言ってるんじゃない、後ろに隠れている奴に言っているんだ。この前も、連れて行って良いのかと聞いたら、『どうぞ。』と簡単に言いやがったから連れて来たんだ。迎えにやって来るとは度胸がある奴なのかと思ったが、どうも違う様だな。メドゥルノとか言ったか、お前が連れて来たんだろう。あいにくだが、お前と勝負する気は無い、後ろの情けない奴を連れてとっとと帰ることだな。」
ハヤブの言葉に、メドゥルノの体の震えが止まった。
こいつは悪い奴では無いのかもしれないと思えてきた。
暫く睨み合っていたが、
「さあ、どうするんだ。」と切り出したハヤブに、メドゥルノは、
「ボクと勝負しろ。」と、一歩踏み出した。
「嫌だね。」と言って、後ろを向いたハヤブに、「ヤアー。」とメドゥルノは飛び掛っていった。
しかし、ハヤブはヒョイと身を交わし、振り返るや否や大きな口を開けてメドゥルノに噛み付いてきた。
「しまった。」と思ったが、相手の素早さに動けないままうずくまった。
「やられた。」と思ったメドゥルノだったが、頭を上げると、自分の前にシズカが居て、その前にハヤブが倒れていた。
起き上がったハヤブは、シズカの方を見て、
「本当は強いんじゃないか。オレの負けだよ。」と言って、その場を離れていった。
遠くで見ていたシズカの友達が駆け寄って、
「見ていたわ。迎えに来てくれたのね。ありがとう。」と言い、シズカの横に擦り寄った。
メドゥルノはショックを受けながらも、これで良かったのだと自分に言い聞かせ、住処へ帰って行った。
途中で、ヒトミとアンドリューおばさんが待っていた。
心配になったヒトミとガーがアーの所まで行って、変な奴とメドゥルノが一緒に出掛けて行ったと聞いたからだった。
「心配ばかり掛けて。」と怒るヒトミに、
「ゴメン、ゴメン。」と、いつもの調子で誤るだけのメドゥルノだったが、今日あったことを話すことは無かった。
メドゥルノの様子が少し可笑しいと感じたのか、アンドリューは何も言わずに見つめていた。
そして、数日後、また事件が起こった。
オチビが血相を変えてメドゥルノの所へやって来た。
「大変だ。ヒトミちゃんが連れて行かれた。」と言うのである。
オチビの話では、ヒトミと話をしていた時に、大きなメダカが現れて、
「やあ、お嬢さん。」と近寄ってきたらしい。
「あっちへ行け。」って叫んだら、
「よお、そこの小さいの。オレと勝負しないか。掛けるのはこのお嬢さんだ。お前が逃げたなら、お嬢さんはオレが連れて行くぜ。」と、迫ってきた。
「『良いから、逃げるんだ。』と言ったのに、ヒトミちゃんの方から、あいつにぶつかって行ったんだ。そうしたら、あいつはヒトミちゃんを追い詰めて来て、ボクみたいな小さいのが間へ割り込んでも一蹴りで飛ばされて歯が立たなかったよ。」
メドゥルノはオチビに、そのメダカの特長を聞いて、
「やっぱり、ハヤブだ。」と一言残し、飛び出していった。
メドゥルノは、先日、シズカと訪れた林の奥へ来ていた。
そこには、顔色を変えて後ずさりするヒトミと、ヒトミに擦り寄ろうとするハヤブの姿があった。
メドゥルノに気付いたハヤブは、笑みを浮かべてメドゥルノの方へ近づいてきた。
「お前は、この前の威勢の良い奴じゃないか。今日は一人でお出ましかい?」というハヤブに、
「ヒトミに何をするんだ。」とメドゥルノは睨み付けた。
「あのお嬢さんはヒトミと言うのかい。可愛い子だから一緒に遊ばないかってお願いしていた所だよ。」
「嫌がっているじゃないか。」
「そんな事があるものか、こうして優しくしてやれば喜んでくれるものだよ。」と言いながら、寄り添う振りをした。
「お前なんかに、ヒトミを渡すものか。」とメドゥルノが言うと、
「おや、ヒトミちゃんはお前の彼女なのかい。」と睨み返して来る。
引き下がれないと思ったメドゥルノは、「ああそうだ。だからボクが連れて帰る。」とヒトミの傍へ寄った。
「ならば、この前みたいに勝負しようじゃないか。女の子は強い男に付いてくるものだぜ。」
ハヤブとメドゥルノは、しばらく睨み合いを続けたが、一瞬の隙をついてハヤブがメドゥルノに飛びついた。交す事が出来ずに倒れたメドゥルノ。起き上がった所へ、ハヤブは容赦なくぶつかってくる。たまらなくなったメドゥルノは、逃げ惑うばかりだった。
それでも、ハヤブはしつこくメドゥルノを追ってきた。
岩と岩の間に追い詰められて逃げ場を失くしたメドゥルノに、ハヤブは体当たりしてきた。
「冷静になるんだ。奴は前しか見えていない。岩の間に突っ込んできた時に下からすり抜ければ後ろに回れる。」と考える間に、ハヤブの頭はメドゥルノのエラの上まで突進して来ていた。
「今だ。」
メドゥルノは、体を半回転して腹ばいになり、ハヤブの下を潜り抜け出た。
その弾みでハヤブは頭を岩に強打して倒れた。
メドゥルノは振り向き、
「大丈夫か。」と近寄った。
ハヤブは息を切らせて横たわりながら、
「今がチャンスだぜ。何故ぶつかって来ない。」と言った。
メドゥルノは、
「ボクは、ヒトミを呼びに来ただけだよ。」と一言残して、ヒトミと共に帰って行った。

|
| 第17話 無力の恐怖 |
|
それ以来、ハヤブの話を聞かなくなり、安心していたメドゥルノ達だった。
ある日、いつもの様に食事に出掛けたメドゥルノは、食事場所から少し離れた所に大きなメダカが浮いているのを見つけた。
近付いて行くと、そのメダカはハヤブだった。
岩にぶつけた頭の部分が腫れ上がり、ヒレにも白い綿状のものを着けている。
口をパクパクさせながら横になり、話すことも出来なさそうな様子だった。
「助けてくれ。」と、小さな声を出した。
「大丈夫か。」と、メドゥルノは駆け寄り、胸ビレで扇いで口元へ水を送り込んだが、他にどうすることも出来なかった。
ハヤブは、最後の力を振り絞りメドゥルノの方へ向き直ると、ほとんど動かなくなった口で、「お前に会えて良かった・・・。」と言った後、また横倒しになった。
エラを押して動かそうとしたが、口もエラも二度と動くことは無かった。
「何故こんなことに・・・。」動かなくなったハヤブの姿を、メドゥルノはじっと見ていた。
ヒトミが近づいて来て、
「罰が当たったのよ。」と憎そうな顔をしたが、
「ハヤブだって、本当は悪い奴じゃないんだ。」と傷つけてしまった自分に後悔していたのだった。
そこへ、オチビがクネクネと回りながら浮き上がってきた。
「何だか調子が良くないんだ。」
メドゥルノとヒトミは、オチビの姿を見て驚いた。
オチビは、背中の横が少し曲がって白い粉を吹いたようになっていた。さらに、口先やヒレの先にも白い綿のようなものがぶら下がっていた。
「オチビ。君もか。」
その姿は、先ほど目の前で動かなくなったハヤブと同じような症状だった。
メドゥルノはオチビの体に付いた綿状のものを口で取り始めた。
「そんな事をしても治らないわ。うつったらどうするの。」と止めるヒトミに、
「構うものか。」とメドゥルノは止めようとしなかった。
そのやり取りを聞いていたオチビは、急に泳ぎ出し、
「こっちへ来るな。」と言って、潜っていった。
追い駆けようとするメドゥルノの前にヒトミは立ち塞がり、
「バカッ、オチビの気持ちが分からないの!」と睨み付けた。
正気を取り戻したのか、メドゥルノは泣きながら、去っていくオチビを見ていた。
「オチビだけじゃないかもしれない。心配だわ。」
ヒトミは、小さい頃にアンドリューおばさんから聞いたという話を始めた。
「こんな話を聞いたことが有るの、昨年の秋、夏の暑さで弱っていた子達は、涼しくなって元気を取り戻したのに、体中に白い斑点が付き始めて、体中が痛くてうまく泳げなくなったらしいの。斑点が出ても動くことができる力のあった子や、大きな大人は痛みに耐えることが出来て、冬になれば治まったのだけれど、小さい子や弱い子とか体のどこかに傷を負った子は、皆動くことが出来なくて食べることも出来なくなったので、生き残れなかったのだって。同じかどうか分からないけれど、他の子にうつっていなければ良いのだけれど。」
メドゥルノはそれを聞いて、
「近くを見て回ろう。」と言い出した。
メドゥルノとヒトミは、住処の周辺に居る仲間達を見て回った。
ヒトミが一匹のメダカを見て、「アッ、あの子は?」とメドゥルノを呼び止めた。
「彼女はフタホシじゃないか。」
「そう、フタホシちゃんよ。」とヒトミが近寄って声を掛けた。
「具合が悪いんじゃない。フタホシちゃん。」と聞くと、
「体がしびれて、目が良く見えないの。」と答えてきた。
フタホシの頭も白い綿をかぶったようになっていた。
「少し流れのある所へ行って新鮮な水で体を洗ったほうが良いわね。」と言うヒトミの言葉に、フタホシは、
「そうね。そうするわ。」と、重たそうな体を引きずって流れのある方へ泳いで行った。
メドゥルノとヒトミは、近くで動かずにいる子達に流れのある所で体を洗うように言って回った。
だが、周辺を見て回ると、白い綿のようなものを付けている子は、次々と見つかった。
ヒレに綿が付いている子は体に感じることが無いらしく、
「変なのが付いて泳ぎにくいけれど、体調は良くって元気一杯だから大丈夫だよ。」と心配していない様子だったけれど、シズカ達に突かれたことがある子や岩などに体をぶつけて傷を負った子は、決まったように傷の部分に綿のようなものが生じて体調を崩していた。
「とにかく、体を洗うことしか防ぐ手段が無さそうだから、僕達も涼しい流れで洗ってから帰ることにしよう。」と、メドゥルノとヒトミは体を洗って住処へ帰った。
次の日の朝、メドゥルノは体が重いように感じた。別に、動くことが出来ないような感じではなかったが、何となく昨日までのように俊敏に動くことが出来ずにいた。
それでも、「食事に行かないと。」と思い、ゆっくりと浮き上って行った。
途中でヒトミとデブッチョに会った。
ヒトミ達も食事に行く途中のようであった。
「やあ、ヒトミちゃん、デブッチョと一緒に食事かい?」と聞いたメドゥルノを見て、
「メドゥルノ、具合が悪いんじゃないでしょうね。」とヒトミが言い出した。
メドゥルノは強がって、
「エッ、何故?、別にどうも無いけれど。」と答えたけれど、
「だって、様子が変だもの。」と、気付かれたみたいだった。すごい直感だなあと思いながらも、「気のせいだよ。」と言っている傍から、メドゥルノの体の回りをヒトミが見て回っていた。
そして、「やっぱり。」と大きな声を上げた。
「エッ、どうしたんだい。」
「メドゥルノ、背中に白い綿のようなものが付いている。」と後ずさりしながらヒトミは言った。
「そんな。」、メドゥルノの目の前を黒い影が過ぎった。取ってくれ。とは言えるはずも無い。
「近付かない方が良いよ。」と言って、メドゥルノは食事を止めて引き返した。
背中には痛みもかゆみも無く、付きまとっているものがあるとは信じられなかった。
「取りあえず、やれることをやるしかない。」
メドゥルノは、ヒトミが言った背中の部分を岩に擦りつけたり、流れのある所で体を洗ったりを繰り返していた。
次の日も、その次の日も、メドゥルノは食事をすることも無く、仲間が居る住処へ帰ることも無く過ごし、やれることを繰り返していた。
しかし、メドゥルノの体は重くなるばかりで、ヒレを動かすことも十分に出来なくなってきた。
そんなある日、流れる水に向かって体を洗っていたメドゥルノの前に、痩せこけたオチビが流されてきた。オチビの体は全身が白く濁り、頭や背中、ヒレのいたる所がちぎれそうに荒れて、口にまで綿のような白いものを銜えていた。
「メドゥルノじゃないか。」と、腫れ上がった目で、こちらを見て叫んだような気がした。
流れのままに、白い腹を見せては、荒れてただれた背中を見せながら、流されて行った。
メドゥルノが見たオチビの最後の姿だった。
次の日、メドゥルノは口に何か付いていることに気付いた。それが邪魔でうまく口が動かせ無かった。どんどん悪い方へ進んでいる事は分かっていた。それでも、今日も体を洗いに流れのほうへ向かった。流れの中では、流されまいと胸ビレを動かすのがやっとだった。尻尾は、ほとんど動かすことが出来なくなっていた。
「もう、駄目かもしれない。」
「いやだ!ボクは生きるんだ。」
流されまいと、必死で胸ビレを動かした。
目の前が真っ青になってきた。見えるもの全てが青い。そして、青い水の世界がメドゥルノを優しく包み込んだ。
青い水と共に、アンドリューおばさん、アー、ガー、ビャー、オチビ、デブッチョ、チカラモチおじさん、・・・・・そして、ヒトミの姿が次々と目の前を過ぎっていった。
「皆、置いていかないでくれ・・・・・。」
目が覚めたメドゥルノは、まだ青い水の世界に居た。体中がピリピリと針に刺されたように痛かった。メドゥルノの下にはゴワゴワした物が茂っていて、尻尾と左の胸ビレは茂みの中に潜り込んでいる。口には何か大きな物が付いているみたいで、きちんと閉じることが出来なかった。動く力も無いメドゥルノは、時が流れるままに青い水の世界を眺めていた。
次第に青が明るくなって来る。遠くの方に黒い影が一つ動いている。黒い影は段々と近づいてくる。そして、その後ろからまた黒い影が一つ、また一つ。そのうち、十数個の影が重なり合って固まりになっていく。近づくに連れて黒い影が青くなってきた。
「待てよ。青いけれど、あれはヒトミじゃないか。」
黒から青に変わった時には、すぐ目の前まで来ていた。
「メドゥルノ!」と青い影が叫んだ。
「夢ではないのか?」と思った。
「メドゥルノ、私よ、分かる?」
「これは、夢なのかい?」
メドゥルノの口は、大きな物が付いたままで、うまく喋れなかった。
青い水に染まったヒトミの顔がそこにはあった。
「神様、最後に会わせてくれたんだね。感謝しています。」
メドゥルノは夢うつつのまま眠ってしまった。
そして目覚めた時も夢の世界のまま、ヒトミの青い顔がメドゥルノを見ていた。
「やあ、また会えたね。」
今度は、口に付いた物は無くなっていて、普通に喋ることができた。
「何言ってるの。もう動くことが出来るでしょう?」と言って、ヒトミは胸ビレでメドゥルノの体を撫ぜた。
メドゥルノが、二三度、尻尾を振ると埋もれていた体が浮き出て、泳ぐことが出来るようになっていた。
「まだ少しバランスが取れないし、所々痛いけれど大丈夫みたいだ。」
「良かった。」と、ヒトミは笑った。
「それにしても、何故こんなに青いんだ。」
ヒトミは、メドゥルノが眠っている間に起きたことを話してくれた。
メドゥルノが住処から居なくなった後も、次々と綿のような物が付く病の子が出てきた。何匹かの重症の子は何も出来ないままに動けなくなって浮き上がって行った。そして、ヒトミも体が重くなってきて、周辺の全員に移ってしまった様だった。希望を失いかけた時、水の流れが真っ青になって住処を包んできた。
「青い水に触れるとピリピリと痛くて、皆叫んでいたわ。私も気を失ってしまったみたいで、気が付いたのは次の日の朝だったの。その時は、今よりもずっと青い水に覆われていて、近い所でも良く見えない程だった。でも、痛みは治まっていて、体も軽くなっていた。きっと、この青い水が治してくれたのよ。」
数日して、青い水は徐々に薄くなり、元の世界へと戻った。
しかし、メドゥルノとヒトミが戻った住処の周辺に残っていたのは、半数の仲間だけだった。
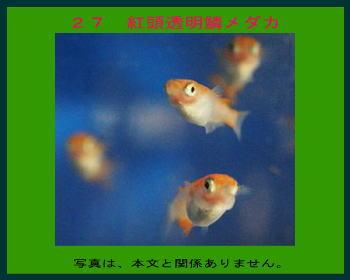
|
| 第18話 冬が来る |
|
元の生活に戻って、食事も出来るようになったメドゥルノは、日に日に元気を取り戻した。
次第に秋も深まり、冷たい水に体を震わせて眠る日が多くなってきた。
メドゥルノは、回復してから一度もアンドリューおばさんに会っていなかった。
「会いたい。」と言うヒトミの誘いもあって、ふたりで様子を見に行くことにした。
途中、周辺の仲間達の様子を見ながら向かっていたふたりだったが、余りの変わりように驚いた。
「ここでも、綿病が出ていたんだ。」とメドゥルノが思うように、いつも通るたびに挨拶してくれた仲間達がほとんど居なくなっていた。
「まさか、おばさんも。」と、アンドリューおばさんが心配になったメドゥルノは、
「急ごう。」とヒトミを急き立てた。
アンドリューの住処に着いた時、アンドリューは居なかった。近くに居た子に聞くと、ここは夜冷たいので暖かい場所を探しに行くと言って出かけたと言うのである。
「でも、無事だと分かって良かったわ。」というヒトミを尻目に、メドゥルノはアンドリューを捜し始めていた。
「暖かい場所を考えれば、流れが無くて陽が当たる場所だろう。」と言って、林の辺りや岩山の麓を捜して回った。
そして、林と岩が途切れた隙間に潜り込んでいるアンドリューを見つけたメドゥルノは、
「アンドリューおばさん。」と呼びかけた。
アンドリューは優しい目で、
「おや、メドゥルノとヒトミちゃんじゃないの、無事で良かったわね。」と答えた。
「アンドリューおばさんも無事で良かった。」と安堵したふたりだった。
そして、アンドリューは、また話を聞かせてくれた。
「皆、病気になってしまって大変だったわね。私達も青い水が来るまでに沢山の大人たちが旅立ってしまったわ。もう、残っている年寄りは私だけになってしまった。私も、例の病に掛かった所が治り切らなくて、まだ体が十分に動かないのよ。だから、今のうちに氷が来ない場所へ移っておこうと思ってね。もう少しすると、上の方は氷で覆われてしまうから。
あなた達の様に若い子は、氷が張り始める前に食事をたっぷりと取って体力を蓄えないと、春まで生き残れないから、今のうちにしっかり準備することね。氷が張り始めたら、絶対に底の方でじっとしていないと、氷に絡まれると命を落とすから注意をしないとね。」
「おばさんは、もう食事をしなくてもいいの。」とヒトミが尋ねたら、
「私は大丈夫よ。ここで春まで眠るつもりだから。」と言って、奥の方へ入って行った。
「無事だと分かったし居場所も分かったのだから大丈夫だよ。春まで眠らせてあげよう。」と、ふたりはアンドリューの寝床を後にした。
病気の影響で体も弱り細くなったメドゥルノ達は、食べることに努めた。おかげで、冬が来る頃には、元の太った体に戻って来ていた。
今日は、食事に来ているアーとビャーに、久しぶりに会った。
「ガーはどうしたの?」とメドゥルノが聞くと、ふたりは食べるのを止めて、
「ガーは、病気で亡くなったよ。」とつぶやいた。
「あの変な奴に突かれた傷口がすぐに白くなって腫れ上がり動けなくなったんだ。ガーは病気の進むのが早くて、青い水が来るのを待てずに逝ってしまった。最後は狂ったように暴れ回っていたよ。」
「ガーは、ボクを助けるために身代わりになって、あの変な奴に突かれたから・・・。」アーの目から涙がこぼれた。
「そんなこと無いよ。」メドゥルノは、それ以上何も言えなかった。
それから、さらに日は過ぎて、一層、水の冷たさは増していった。
昼間でも、仲間は皆、住処から離れることが無くなり、食事場所へ行く子は少なくなってきた。
けれども、メドゥルノだけは少しでも体力を蓄えなければと、できる限り食事には行く様にしていた。
食事場所へ集まるメダカも少なくなり、秋までの賑わいは無くなっていたが、その分食べ物は豊富に残っていて満足できる状態であった。
メドゥルノは、そこでデブッチョに出会った。
デブッチョは、タダでさえ丸かった体が一段と丸くなって泳ぐのも大変そうであった。
「やあ、デブッチョ。今日も来ていたんだ。」
「やあ、メドゥルノ。ボクは毎日来ているからね。今は、食べ物が一杯あって食べ放題だよ、皆が居る時は中々食べられないから、今のうちにたっぷり食べておかないと。」
「ハハハッ。でも、デブッチョの体はまん丸になっているよ。食べすぎじゃ無いかい。余り食べ過ぎると泳げなくなっちゃうよ。」
「大丈夫だよ、ほら。」と言って、デブッチョはやや重たそうではあったが、元気に泳いで見せた。
次の日も、その次の日も、水は冷たかったけれど、メドゥルノは食事場所へ出掛けた。
行く度に食事に来ているメダカが減り、食べ物だけが浮いているようになってきた。
けれど、デブッチョにだけは、毎日、会うのだった。
「もう、ボクとキミだけしか食事に来なくなったね。」とメドゥルノが問いかけると、
「そうだね。」と言いながらも、デブッチョは、まだ食べ物を突いていた。
「そろそろボクも春まで底の方で眠ることにするよ。春まで、お別れだね。元気で冬を越すんだよ。」とメドゥルノが告げた。メドゥルノは、今日は最後の食事にして暖かくなるまで底で眠ろうと決めていたのだった。
でも、デブッチョは、「そうだね。」と言って、また食べ物を突いていた。

|
| 第19話 諦めるんじゃない |
|
その日は、凍るような冷たい夜だった。皆、身動き一つ無く眠っていた。
それでも、明るくなり明かりが差し込んでくると暖かくなって来る。目が覚めたメドゥルノは、少し暖かくなるとじっとして居られなくなり、迷っていた。
「それにしても、周りの仲間は良くずっと眠っていられるなあ。起きてしまったから、今日もやっぱり食事に行こうか。」と考えていると、昨日のデブッチョの姿が頭に浮かび、何やら胸騒ぎを感じた。
もしかすると、デブッチョは冬が来ると氷に閉ざされることを知らないのかもしれない。
冬の仕度をして底で眠りに付かなければいけないのに、何もしていない様だった。
そうだ、もう一度、食事場所へ行ってデブッチョに言って来なければ。
メドゥルノは、今日こそはと決めて、食事場所へと向かった。
今日も、食べ物は沢山浮いていたが、明かりは次第に弱くなって、刻々と水は冷たくなって来ていた。
メダカの姿は見られない。
「こんなに冷たいのに、居るわけが無いだろう。」
周囲を見渡したメドゥルノは、少し離れた所に赤い丸いものが浮いているのを見つけた。
「居た!」
やはり、デブッチョは今日も食事に来ていた。
メドゥルノは近寄って、
「やあ、デブッチョ。話があるんだ。」と言うと、
「何だい?」と言いながら、横目でメドゥルノを見るなり、背を向けてしまった。
メドゥルノは、背中越しに話を続けた。
「キミは知らないのかも知れないけれど、もうすぐ、この辺りは氷で閉ざされてしまうんだ。何時までもここへ来ていると、凍り付いて動けなくなってしまうかもしれない。」
すると、デブッチョは、
「そんなことは分かっている!」
「ならば、何故誰も居なくなっているのにキミだけがここに居るんだ。」と言っても、
「メドゥルノだけだね、心配して来てくれるのは。でも、ボクは大丈夫だから、メドゥルノも早く帰って眠った方が良いよ。」と聞き入れない。
「何故なんだ!」
メドゥルノは怒った様に叫んだ。
「ボクは、底へは行けないんだ。」
デブッチョは泣きながら振り返った。
「こんな体だから、自分では下へ泳げ無いんだ。何度も何度も下へ行こうとしたんだ。でも、どれだけ頑張っても、すぐに水面に浮いてしまうんだ。」
その時、パリッという音がした。横の方を見ると、凍り始めた水の間から泡が出て氷を裂くように抜けていくのが見えた。
メドゥルノは急がなければと思った。
「ボクが引っ張ってあげるから、一緒に底まで行こう。」
「そんなことが出来るものか。キミもボクの巻き添えになってしまうじゃないか。」
デブッチョはメドゥルノを振り切って逃げようとしたが、ほとんど動けない状態になってしまっていた。
メドゥルノは、デブッチョの胸ビレを銜えて引っ張った。
「尻尾を振るんだ!」
デブッチョの体は少しだけ水中へ下がった。
けれど、すぐに泳ぎを休めてしまうと、胸ビレを引っ張る程度の力では止めることが出来ずに、水面に勢いよく浮き上がってしまう。
「もう一度、頑張るんだ。」
メドゥルノが胸ビレを銜えて、デブッチョは尻尾を振る。少し下がっては、すぐに浮き上がる。
ふたりは何度も繰り返した。
周囲は薄暗くなり、水面には氷の膜が覆い始めていた。
「諦めるんじゃない。」
と励ましながら夢中で泳ぐメドゥルノだったが、メドゥルノのヒレも動きが弱くなって来た。
最後の力を振り絞り全力で引っ張り続け、中程まで降りてきた。
「そうだ、その調子だ。底まで行って潜り込めば浮き上がらなくなるから。」
メドゥルノは叫びながら引っ張り続け、底の岩に届きそうになった時、デブッチョの体は急に重くなってメドゥルノの口から外れた。
「もう無理だよ。」と一言残し、動かなくなったデブッチョは、静かに浮き上がって行った。
「待ってくれ、デブッチョー。」と叫んだメドゥルノだったが、追いかける力は残っていなかった。
まるで空を舞うように静寂の中を遠ざかる姿は、輝いて見えた。
彼は、きっと生き残ってくれると信じて止まないメドゥルノだった。

|
| 第20話 意識だけの世界
|
|
その夜から、水面は氷で閉ざされ、永い永い眠りに着いた。
メドゥルノは、夢の中で何度も目が覚めた。
目が覚める度に、誰も居ない、何も動かない、静まり返った住処を見て寂しさを感じた。
「皆、どうしているだろう。」
何も答えてくれなかった。何処かで水の動くような音だけが小さく流れていた。
今すぐにでも泳いで行きたい。けれども、ヒレも尻尾も冷たさに痺れて動かなかった。自分の体が無いような意識だけの世界は、一日が何年もの月日のように永く感じた。
ただ耐えるだけしかないメドゥルノだった。
そんなメドゥルノを心配したのか、アンドリューおばさんが会いに来てくれた。
「アンドリューおばさん。」とメドゥルノが呼ぶと、
「私は元気で居るから安心してね。」と囁いて、また帰って行こうとする。
「おばさん、一緒に眠りたいよ。ボクも連れてって。」と呼び止めた。
「わがままを言わないの、すぐに春が来るから。春になれば、また、皆と会える。たくさんお話しましょうね、楽しみだわ。」
「ハッ。」メドゥルノは、また目が覚めた。
そこには、誰も居ない住処の景色と小さな水の音だけがあった。
「おばさん、春になれば一番に会いに行くからね。」とつぶやいて、また眠りに着いた。
「メドゥルノ、メドゥルノ・・・。」
次は、誰かに頭を突かれて目が覚めた。
「何時まで寝ているの?」
頭を突いていたのはヒトミだった。
「今度はヒトミちゃんが会いに来てくれたんだ。」とメドゥルノの夢事に、
「何言ってるの、こんなに暖かくなっているというのに、何時まで経っても起きないんだから。もう食事に出掛けている子も居るわよ。」
「エーッ。」と、メドゥルノは飛び起きた。
「本当だ。ヒレも動くし、尻尾も楽々だ。春が来たんだ。」
「そう言えば、お腹空いたね。」
「あきれた。」

|
| 第21話 春なのに |
|
早速、メドゥルノとヒトミは食事に出掛けることにした。
食事場所には、沢山の仲間達が来ていた。
アーやビャーもいた。
「アッ、チカラモチおじさんもいる。」
「おじさん、久しぶり。」とメドゥルノが話しかけると、
「メドゥルノじゃないか、元気で良かった。」と答えてくれたが、キョロキョロと水面を見ながら何か落ち着きが無い様子だった。
「どうしたの?」
「五日も前から毎日来ているんだけれど、食べ物が降って来ないんだ。皆、腹ペコだろうから早く食べ物を見つけないと騒ぎが起こるぞ。」
「それで、皆ソワソワしているんだね。」と納得していると、
「春は大切な時期だから、何とかしないと。」と言いながらも、チカラモチには術が無い様であった。
メドゥルノは、夢の中で会ったアンドリューおばさんの事を思い出し、
「それならば、アンドリューおばさんに聞いてみればどうかな。」と聞いた。
「そう言えば、アンドリューはまだ見て無いなあ。」との事だった。
メドゥルノとヒトミは、
「きっと、あの岩陰で、まだ眠っているんだよ。仕方ないなあ。」と話しながら、アンドリューが冬眠している筈の場所へ向かった。
しかし、そこにアンドリューの姿は無かった。
「可笑しいなあ、この辺りの筈だよ。」
「そうよ、最後に見に来た時も、この岩の間で眠っていたもの。」と、氷が張る直前にヒトミも見に来たことを話していた。
「住処に戻っているのかもしれない。」と思ったふたりは、住処へも行って見たが、アンドリューは居なかった。
近くに居る子に手当たり次第聞いて見ても、誰も、「知らない。」の一言だった。
その日、メドゥルノとヒトミはアンドリューを見つけることが出来ないまま帰ることになった。
次の日、
「食事に行きましょう。」と言うヒトミに対し、
「ボクは、アンドリューおばさんを捜す。」と突っぱねたメドゥルノだった。
上の方でザワザワと音がする中、ひとりアンドリューを捜していた。捜せる所は全て捜したメドゥルノだった。出会った子には、皆尋ねた。でも、アンドリューは見付からなかった。
メドゥルノは空腹で目の前がかすんで見えた。
水面へ上がった時には、食べ物は欠けらも残っていなかった。
そのうちに辺りは暗くなり、夜を迎えようとしていた。
「おばさん、一番に会いに行くと言ったのに、約束守れ無かったよ。」
近くにあった岩にしがみ付いて眠るメドゥルノだった。
次の日から、食事を済ませてから捜すことにした。
目覚めてすぐ食事場所へ向かうメドゥルノに、一匹のメダカが襲い掛かってきた。
「何をする!」と叫んだメドゥルノに、
「何か食わせてくれ。」と、そのメダカは叫んだ。
「まさか!」と思い、辺りを見渡すと、あちらこちらで追い掛け合うメダカの姿があった。
「まだ、食べ物は降って来ないのか?」
「そうだ。食えそうなものは全て食べ尽した。残っているのはメダカだけだ。このままでは死んでしまう。」
「もう少し、我慢して待とうじゃないか。」と言って食事場所へ向かおうとしたメドゥルノだったが、他のメダカ達も殺気立って次々と襲って来る。
小さい子達は逃げ惑い、逃げ場を失った子が飲み込まれた。
メドゥルノのヒレも、襲って来た大きなメダカに削ぎ取られて傷ついた。
傷ついたメドゥルノは体が傾いてうまく泳げ無くなり、ヒレを動かしても進まない。
気付いた時には、傷を負ったメドゥルノの周りをメダカ達が囲んでいた。
闘っても勝てないと諦めたメドゥルノだった。
メドゥルノは仰向けになり、胸ビレを広げた。
「食いたければ食えばいい。でも、ボクだけでお前達の腹は満たせるのか?お前たちも共に食い潰し合うだけじゃないのか。」
囲んでいたメダカ達は、一瞬、立ち止まった。
しかし、中に居た一匹が、「構うものか。」と、メドゥルノの腹を目掛けて飛び掛ってきた。
次の瞬間、大きな影が下から突進して来て、飛び掛ろうとするメダカを跳ね返した。
「いい加減にしろ!」
それは、チカラモチおじさんだった。
おじさんは、メドゥルノの前に立ち塞がり、
「俺が相手だ。掛かれるものなら掛かって来い。」と、すごい剣幕だった。
囲んでいたメダカ達も後ずさりしながら、睨み合いは続いた。
その時、大きな影が頭上を遮り、食べ物が降ってきた。
皆、一転して歓声を上げ、何事も無かったかの様に散らばって行った。
メドゥルノは、泳ぎにくくなった体で食事をしながら、チカラモチおじさんと話をした。
「昨日まで、アンドリューおばさんを捜していたのだけれど、見付からないんだ。」
「ボクもまだ会っていないなあ。最後に見たのは、あれは。」と、思い出したようにチカラモチおじさんは夢の話を始めた。
「真冬の冷たい日の事、目が覚めたらアンドリューがこちらを見ていたんだ。一言、『ありがとう。』と言った様な気がしたけれど、良く聞き取れなかった。呼び止めようとしたが、ヒレが動かなくて出て行け無かった。アンドリューは這う様にして去って行ったんだ。変な夢だったなあ。」
それを聞いて、メドゥルノは、
「ボクも同じ様な夢を見たんだ。」と言うと、
「もしかすると、アンドリューは最後のお別れに会いに来たのかもしれない。長老のメダカ達は亡くなる前に身を隠すと聞いたことが有る。」と、チカラモチおじさんは遠くを見ながらつぶやいた。
「アンドリューおばさん、ありがとう。」と、メドゥルノは大声で叫んだ。
この春、アンドリューを見掛けた者は誰も居なかった。

|
| 第22話 恋の季節 |
|
食事場所にも、高い岩の上にも、林の間からも明るい日差しが入り込み暖かい日が続く様になった。
男の子達は皆、濃い赤色に着飾り、徘徊して回る、恋の季節がやって来た。
女の子達はと言うと、皆、困った様子だった。
「この辺りには男の子ばっかり居て、いつも追い掛けて来るの。どうにかならないかしら。」と、ヒトミがフタスジに、ぼやいていた。
そこへ、また男の子達がやって来て、ヒレを立てて誘って来る。
ヒトミもフタスジも無視していると、近付いて来て背中や腹の下へ擦り寄っては、別の子が突進して来て絡み合いの状態だ。散らばって逃げ出しても、二匹、三匹が交互に追い掛けて来る。
皆が口を揃えて、
「『一緒になろうよ。』って、芸が無いんだから、嫌になっちゃう。」と言いながら男の子達を見ていたヒトミは、
「アレッ、メドゥルノも居るじゃない。」と驚いていると、近付いて来て、
「ヒトミちゃんでも良いや、一緒になろうよ。」
「冗談でしょ。あなたとは友達でしょ。」
「良いじゃないか。この辺には女の子が少ないんだし。」と付いて来るので、ヒトミは尻尾でメドゥルノの頭を叩いて、
「フン。」とお冠だった。
そこへ、また男の子達が押し寄せた。
「あんな奴よりボクの方がずっと良いだろう。このヒレ見てみなよ。」
「何言ってんだ、ボクの方が格好良いだろ。」
何匹もが喧嘩しながら纏わり着いて来る。
見かねたメドゥルノが割って入り、
「嫌がっているじゃないか。」
「何い!」
メドゥルノも混じって、男の子達は絡み合いながら行き去った。
「フウッ。」と一息ついたヒトミだった。
日が傾きかけて水も冷たくなって来ると、さっきの騒然とした騒ぎが嘘の様に静まり返った。
「これから、どうなるのかしら。」と嘆いていたヒトミの所へ、メドゥルノが帰って来た。
そして、「一緒になろうよ。」と囁いた。
「まだ言ってるの。」と言うヒトミに、
「ボクは真面目だよ。生れた時からヒトミちゃんと一緒になろうと決めていたんだ。」
「メドゥルノったら。」
次の日の朝、ヒトミは七つの卵を抱いていた。
「初めての卵だ。」と、何度も数を数えるメドゥルノに、
「もう、余り見ないで。」と、照れくさそうなヒトミだった。
だが、平穏な時間は長く続かなかった。
男の子達がやって来て、卵を抱いているヒトミを見るなり、
「うまそうじゃないか。」と、下から回りこんで来た。
「何をする。」と叫ぶメドゥルノを突き飛ばし、逃げるヒトミを追い掛けて行った。
後を追ったメドゥルノは、ヒトミを囲んでいる男達の中へ突っ込んで行った。
「止めろ。止めるんだ。」
メドゥルノが争っている隙に一匹のメダカが卵を奪い取って逃げた。それを追って他のメダカも去って行った。
「どうしてー。」と泣き叫ぶヒトミに、
「奴らから逃れる策を考えよう。今度は絶対に卵を渡さないから。」と言いながらも、慰め様も無い哀しみに包まれるメドゥルノだった。
落ち込んで、動こうとしないヒトミだった。
「でも、食事には行かなければ。」
メドゥルノはヒトミを引っ張る様にして食事場所へ出掛けた。
しかし、僅かな食べ物が残っているだけで、少し離れた所でも数匹が食べ物の取り合いで騒いでいた。
「やはり、食べ物が少ないから卵を狙って来るんだ。小さい頃、小さい子達が狙われたのと同じ事なんだ・・・。ヒトミは十分に食べなければ駄目だから、しっかり食べるんだ。少ししか残っていないけれど・・・。」
メドゥルノは、残っていた食べ物をヒトミに譲り、奴らが近付いて来ない様に見張っていた。
「卵を守るためには、早く、見付からない所へ産み付けるしかないだろう。今度は、ボクがやつらの注意を引くようにするから、その間に、なるべく広い範囲へ卵を隠しておくれ。」と、メドゥルノはヒトミに説明した。
数日後の朝、ヒトミは十数個の卵を抱いていた。
「今日こそ守ってあげるからね。」と卵に話しかけるメドゥルノだった。
少しして、何時もの様に男の子達が近付いてきた。
メドゥルノは、「暫くお別れだ。生まれて泳げる様になったら、また会おう。」と卵に囁き、
「ヒトミ、卵達を頼むよ。」と告げて、男の子達が来る方へ飛び出して行った。
メドゥルノは男の子達と絡み合っていた。その間に、ヒトミは産卵場所を探しに住処から離れて行った。
それを見つけた男の子達の一匹がヒトミを追い掛け様とする。
メドゥルノはそいつに体当たりすると、振り返って来て揉み合いとなった。男の子達に追い詰められたメドゥルノは立ち向かって行き様も無かった。
「逃げるが勝ちだ。」とばかり、男の子達を引き連れるようにして、力の限り泳ぎ回った。
暫くメドゥルノを追い続けた男の子達も、疲れたのか、追うのを止めて食べ物を捜しに散って行った。
口とヒレは傷付き、ボロボロだった。けれど、
「きっと卵達は無事に育ってくれるに違いない。」と思うと、気分は良かった。
夕方になって住処に戻って来たヒトミは、満面の笑みを浮かべていた。

|
| 第23話 後悔の一言 |
|
暫くは闘いの日々が続いたけれどメドゥルノの活躍もあり、少しずつ卵の数を増やしていくことが出来た。
暖かくなるのに従って、食べ物の量も増え、卵を狙うメダカ達も減ってきた。
メドゥルノ達の住処の近くでも生まれたばかりの小さな子が泳ぎ始める様になり、メドゥルノもヒトミも、自分たちの子であると信じ遠くから見守る日々だった。
そんなある日、男の子達の集団に追い掛けられている丸いメダカを見掛けたメドゥルノは、何事かと近寄って行った。
集団の中の一匹が、丸いメダカを追い詰めて、
「二度と彼女に近付くなよ。」と、怒鳴っている。
追い詰められている丸いメダカを良く見ると、アーだった。
「アーじゃないか。」
メドゥルノが声を掛けると、追い詰めて怒鳴っていた子が
「何か用かい。」と迫ってきた。
「キミに用は無い。」と言い返したメドゥルノと睨み合いになったが、横で見ていた子が
「オイオイ、メドゥルノを相手にしてもしょうがないだろう。」と引き止めたので、集団は去って行った。
「大丈夫か。」と気遣ったメドゥルノだったが、
「余計なことをして。」と、アーは不機嫌そうだった。
アーは、この辺りには一匹しかいない丸い女の子と仲良くなって一緒に泳いでいたら、集団がやって来てからかわれたのだった。アーは、彼女を逃がすために、集団に突っ掛かって行って自分の方へ引き寄せていたのだった。
「奴らが彼女の所へ行ったらどうするんだよ。」と心配そうなアーの顔を見て、
「追い掛けよう。」と言ったメドゥルノだったが、
「ボクは早く泳げないよ、追いかけていって争うことなんて出来ないんだから。」と、ふてくされた様子だった。
「他の子とは違って、普通じゃない体だから大変なんだ。」と言ってから、「しまった。」と思ったが、遅かった。
「そうだよ。ボクは普通の体じゃないんだ。」
「そうじゃない。そんなつもりで言ったんじゃないんだ。ゴメン。」と弁解しようとしたら、
「キミだって普通じゃないじゃないか。」と、アーは声を高らげた。
メドゥルノは、分けが分からず、「何が?」と尋ねると、
「恐ろし谷へ行って見て来いよ。」とアーが答えた。
「あんな恐ろしい番人や化け物がいる所へ行って何が分かるんだ?」と聞くと、
「まだ、そんな事を信じているの。番人は鏡に映っている自分で、化け物は水の外の世界に居る生き物だよ。鏡に映っている自分を見てくれば、どんなだか分かるよ。」と、強い口調で言った。
メドゥルノは、アーの言葉に驚きながら、
「分かったよ。恐ろし谷へ行って見て来るよ。」と言って、アーと分かれた。
二度と行くはずの無い恐ろし谷だった。
けれど、アーの言うことが本当ならば、自分が見た番人は自分の姿であったと言う事だ。
メドゥルノは、恐ろし谷へ下る手前の岩上にいた。
ここから見る谷底の景色、底にあるごろごろとした石や、それを取り囲む黒い林は、同じ姿を留めていた。しかし、あの時あれほど恐怖を感じた急斜面も、今見れば単なる下り坂でしかなかった。
メドゥルノは、ゆっくりと谷へ下り、黒い林を抜けて、谷から上を見渡した。
青いばかりの背景の中で遠くに輝く世界と泳ぎまわる影の姿があった。
「これが、自分達を映している鏡だというのか。」
メドゥルノは谷底へ着くなり後ろを振り返った。
そこには、先ほど見渡した世界と全く同じ風景が広がっていた。
明るい光を浴びて食事する子メダカ達や、体を翻して赤と白に輝きながら激しく追い合う雄達の勇壮な姿、卵を抱いて太った体でゆったりと泳ぐ雌達、自分達の日常の生活が目に映った。
「本当だ。恐ろし谷は、ボク達の世界を映しているんだ。」
メドゥルノは後ろを向くのが怖かった。
「何故、怖いんだ。皆と何が違うと言うんだ。ボクだけが、そんなことは無い。」
決心して、メドゥルノは鏡の方へ振り返った。
そこには、一匹の薄黄色のメダカがこちらを見ていた。
「ボクは、赤くないんだ!」
「皆、同じ仲間達は美しい赤色をしているのに、何故、ボクだけ色が違うんだ。」
メドゥルノは、皆と同じメダカの色をしていない自分を知ったショックと、恐ろし谷へ来なければ良かったと思う後悔に、打ちのめされた気がした。
「このまま何処かへ行ってしまおうか。」 ただ呆然と遠くの景色を眺めていた。
すると、景色を掻き分ける様に近付いてくる丸いメダカの姿があった。
メドゥルノは、慌てて逃げ様とした。
「待てよ。」近付いて来たのはアーだった。
「放って置いてくれ。皆でボクの事を見て笑っていたんだろう。」と言うメドゥルノに、
「本当にそう思うのか。ならば、メドゥルノは、こんなボクの姿を見て笑っていたのか?」
メドゥルノは、アーの必死の顔を見た。アーは目に涙を一杯溜めていた。
「誰だって、何処か欠点があるんだ。ボクは生まれた時からこんなだから、沢山の友達に聞いて来たんだ。そして、皆、何か欠点を持っていて、それを補い合うために集まって生きている事を知ったんだ。」
メドゥルノは、取り乱した自分が恥ずかしかった。
「ありがとう、アー。もう大丈夫だよ。」
メドゥルノは、今日あったことは忘れようと思った。
住処へ帰るとヒトミが心配そうに迎えに出ていた。
「急に姿が見えなくなったから、捜したわ。」
「また、心配かけたね。ゴメン。」と、作り笑いをしたけれど、様子が違うことをヒトミには気付かれた様だった。
「どうしたの。何かあったの?」と問いかけてきた。
「別に、何も無いよ。」とごまかそうとしたが、ヒトミが自分のことをどう見ているのかが気になった。
「ねェ。」
「やっぱり変ね。どうしたの。」
メドゥルノは、思い切って聞いてみた。
「ボクだけ、体の色が違うのに、ヒトミはどう思うの。嫌じゃないの。」
ヒトミは、メドゥルノの目を見て、
「別に、何も思わないけれど。遠くからでも分かって良いんじゃない。」
ヒトミのあっけらかんとした言葉に、全てが吹っ切れたような気がした。
しかし、それは、メドゥルノにとって一生を変えることになる事態であることなど、知る芳も無いメドゥルノだった。
(前編 完)

|